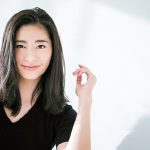Contents
プレゼンの場に立つと、緊張で言葉が詰まってしまう… そんな経験はありませんか? 実は、話し方をほんの少し工夫するだけで、聞き手に伝わりやすく印象に残るプレゼンができるんですよ。
本記事では、プレゼンで一目置かれるための「話し方のコツ」を紹介します。質疑応答のコツやプレゼンの練習方法なども解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
プレゼンのコツ 〜話し方編〜
いいプレゼンには、はっきりとした話し方と分かりやすい資料が大切です。まずは話し方のコツについて。「プレゼンではいつも話し方で失敗してしまう…」という人はぜひ試してみてはいかがでしょうか?

(c) Adobe Stock
聞き取りやすい大きな声で
緊張すると声が小さくなりがちですが、相手に聞き取りやすくするためには、意識的に大きな声で話すことが大切です。口を大きく開け、声のトーンは少し大きめ、話す速度は少し遅めにすることを心がけましょう。
プレゼンの練習にはボイスレコーダーなどを使い、自分の話し方を録音して確認するのが効果的です。聞き手の立場で自分の話し方をチェックできますよ。
分かりやすい言葉を使う
プレゼンでは、誰もが理解しやすい言葉を使いましょう。専門用語や業界用語は、他の人には分かりにくい場合があります。練習の際に、業界知識がない家族や友人に協力を頼んで、分かりにくい用語を指摘してもらいながら、言葉を簡単にしていくといいでしょう。
間をうまく使って相手を引き込む
プレゼンでは、間をうまく使うことで相手の目を引きつけることができますよ。淡々と話すだけでは、どうしても内容が平坦になりがち。重要なポイントを説明する前に一呼吸置いたり、疑問が湧くような部分で問いかけをすることで、聞き手の関心を集められるでしょう。
プレゼンのコツ 〜パワーポイントの資料編〜
プレゼンで使用するパワーポイントは、ただ必要な情報を載せていればいいわけではありません。情報を視覚的に分かりやすく伝えるためには、見栄えと情報量の調節が必要です。よりよいプレゼンをするため、パワーポイント資料作成のコツを紹介します。
見やすいカラー・レイアウトを意識
プレゼン資料を作成する際は、配色とレイアウトに注意が必要です。色はシンプルにし、重要な部分を目立たせるために同系色や濃淡を使うと良いでしょう。色が多すぎると、情報が分かりづらくなります。また、レイアウトは人が自然に目を運ぶ左上から右下の順に配置すると、視認性が高くなりますよ。