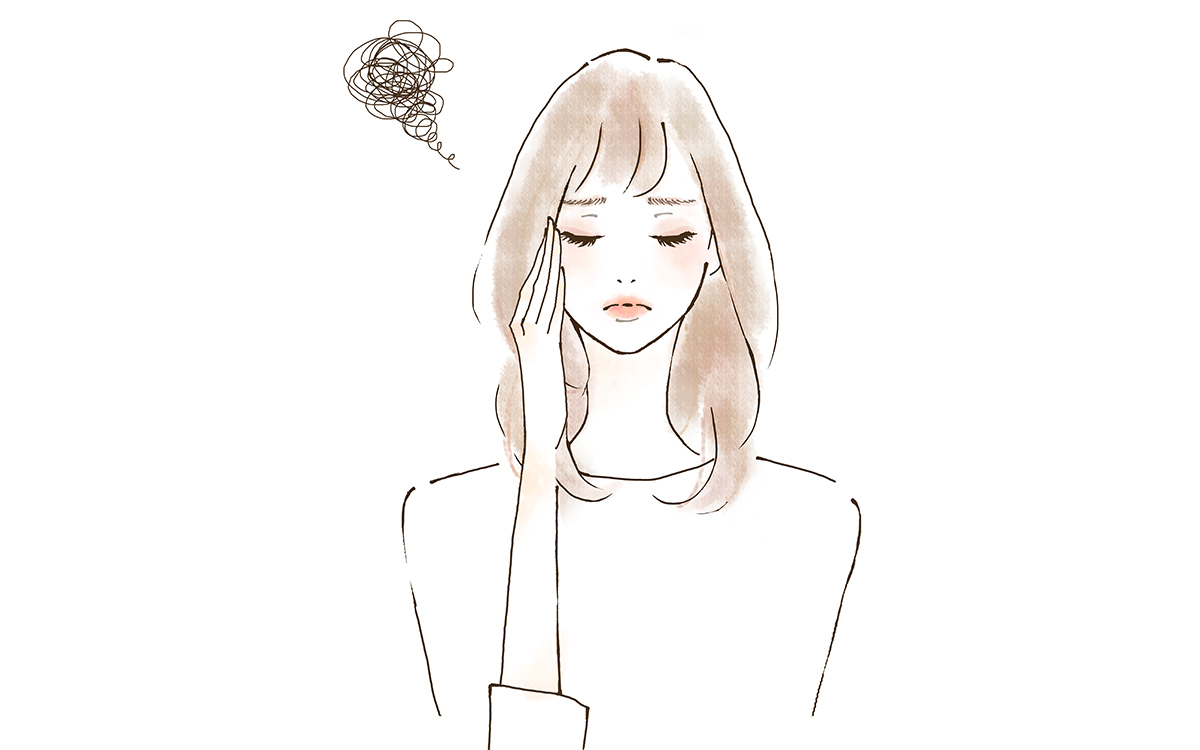誰が見たとしても明らかに危ないと感じる場合には使わず、なんとなくひやひやする、そわそわすると感じるときに使いましょう。
Summary
- 「剣呑」(けんのん)とは、危険そうな様子のことなどを指して使う言葉
- もともとは「険難」と書いて「けんなん」と読む熟語が語源といわれる
- 類語には「危険」「物騒」などがあり、対義語には「安全」「平穏」などがある
Contents
「剣呑」とは?
「剣呑」の意味や由来について、それぞれ詳しくチェックしていきましょう。
「剣呑」の読み方
「剣呑」は「けんのん」と読む熟語です。危険そうな様子のことなどを指して使う言葉であり、不安を感じるようなよくない雰囲気のときには「剣呑な雰囲気」というように表現されます。
同じように「剣吞」と書いて「けんのみ」と読む言葉もありますが、「けんのん」と読む場合とは表現している意味が異なるため注意が必要です。「けんのみ」と読むケースでは、「荒々しく邪険にしかりつけること」という意味になります。
「剣呑」の意味
【剣呑/険難(けん‐のん)】
(形動)ナリ《「けんなん(剣難)」の音変化という》
危険な感じがするさま。また、不安を覚えるさま。
「金は欲しいだろうが、そんな―な思い迄して借りる必要もあるまいからね」〈漱石・道草〉
<派生>けんのんがる<動ラ五>けんのんさ(名)
(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)
「けんのん」と読む場合には、危険を感じている様子やそぶりという意味と、不安を覚えている様子やその雰囲気という意味の2つが表現されます。はっきりとはしていないけれど、よくない感じがするというようなケースで使われる言葉です。
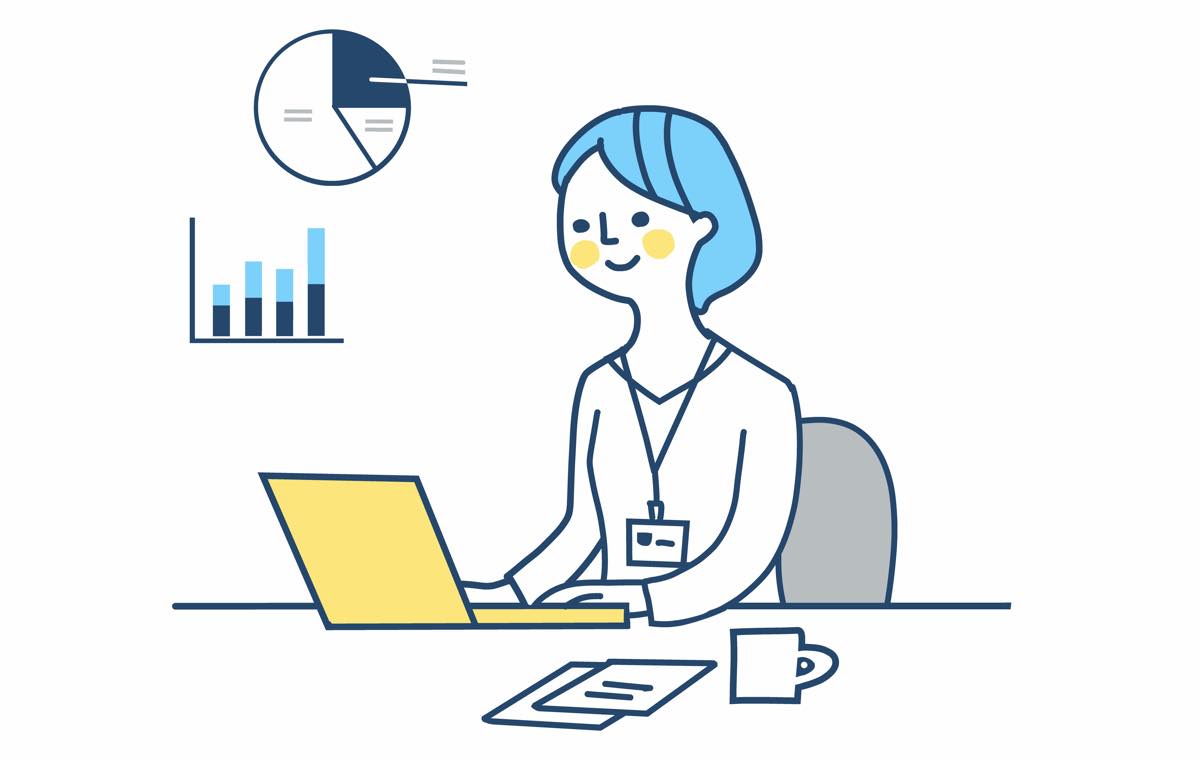
「剣呑」の由来や語源
「剣吞」の由来となった言葉は「険難」です。「剣呑」は、語源である「険難」が変化していった言葉であるといわれています。
なお、現在の「剣呑」という漢字が使われるようになったのは当て字です。「剣を呑む」という明らかに危ない行為が由来となったわけではありません。旧字体の漢字で「剣吞」と表記する場合もありますが、旧字体で書かれていても見た目はあまり変わりません。
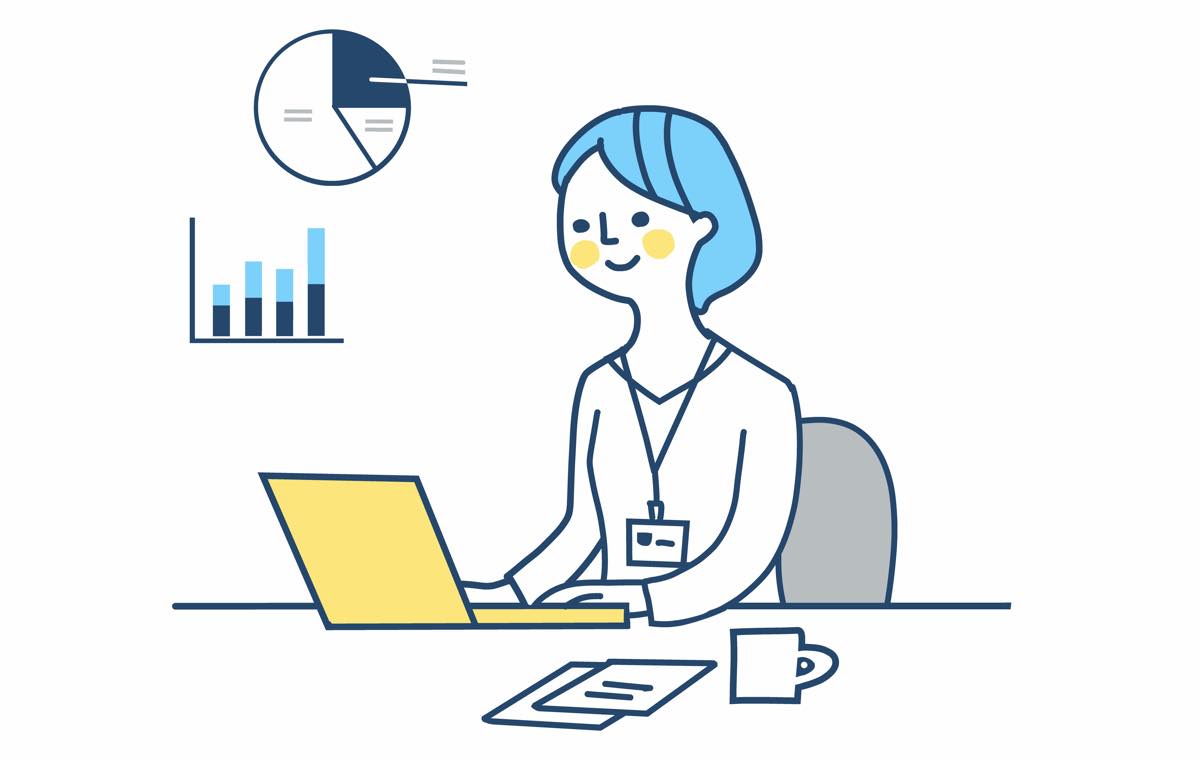
「険難」とは、けわしい災難が予感されるさま、危なくて不安に思うさまという意味の言葉です。
見た目などがよく似ている言葉に「剣難」があります。「剣難」は、刃物で殺傷される災難という意味です。こちらも読み方は「険難」と同じで「けんなん」です。
【実際のエピソード】「剣吞」に関する成功談・失敗談
「剣呑」の体験談には、どのようなものがあるのでしょうか?ビジネスシーンにおいて、「剣吞」に関して何かしらの気づきや学びを得た実際のエピソードを紹介していきます。
【episode1】管理職として、部下の表情を表す言葉として使った経験
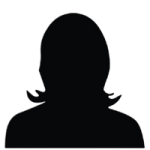
Aさん(管理職、42)
チーム内で評価制度の見直しを説明した際、ある部下が終始無言で、目線も鋭く感じられました。後日、上司への報告で私は「一部メンバーに剣呑な表情が見られたため、個別フォローが必要だと思います」と伝えました。「剣呑な表情」という言葉を使ったことで、「怒っている」「反抗的だ」と決めつけず、不安や警戒心が表に出ている状態として共有できたと思います。実際、その部下と面談すると、制度変更そのものより将来への不安が強かったことが分かりました。感情を断定せず、雰囲気や兆しを表す言葉として「剣呑」を使えたことで、管理職として冷静な判断につながった経験です。
【episode2】人を責める言葉として使われた「剣呑」
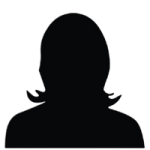
Oさん(管理職、39)
別の部下が、他部署の担当者について「剣呑な人なので関わりたくありません」と話してきたことがあります。しかし、実際は寡黙で慎重なだけの方でした。私は、「剣呑は雰囲気や状況を表す言葉で、人の性格を決めつける表現ではない」と指摘しました。剣呑という言葉を使うことで、相手が危険人物のように誤解されてしまいます。言葉の印象は強く、評価にも影響します。管理職として、便利な言葉ほど慎重に使う必要があると改めて感じました。
「剣呑」の使い方や例文
「剣呑な目つき」や「剣呑な表情」、「剣呑な雰囲気」のように、剣呑を使う場合には多くのケースで「剣呑な~」というように使用します。それ以外にも、「剣呑剣呑」と重ねて使ったり、「剣呑性」と使うこともあります。さらに、派生した言葉として「剣吞がる」「剣呑さ」もあります。

「剣呑な表情」「剣呑な雰囲気」
まずは「剣呑な~」という使い方から確認していきます。「剣呑な」から始まる言葉には、「剣呑な思い」「剣呑な声」などの数多くの表現があります。以下、「剣呑な~」を使った例文です。
【例文】
・クライアントとなかなか条件が折り合わず、ずっと剣吞な交渉を続けている。
・今日は上司がピリピリしており、みんな剣呑な雰囲気を感じながら仕事を続けていた。
・上司は資料に目を落としたまま、剣呑な表情で沈黙を続けていた。
・クレームの話題が出た途端、会議室は一気に剣呑な雰囲気に包まれた。
・彼女の剣呑な表情を見て、これ以上踏み込んだ質問は控えることにした。
・意見が対立し始めると、チーム全体に剣呑な雰囲気が漂い始めた。
・電話を切った後の部長は、誰もが近寄りがたい剣呑な表情をしていた。
「剣呑剣呑」
「剣呑」は、同じ言葉を2回続けて使うこともできます。「剣呑剣呑」というように重ねて使用することで、意味を更に強調しているのです。
このように使う場合は、「くわばらくわばら」や「危ない危ない」と同じ意味で使われています。つまり、危険を感じて災難を避けるために近づかないでおこうという言葉です。また、危険度や恐怖心を強く表現するために使われるケースもあります。
【例文】
会議の後半は、誰も本音を言わなくなって、なんだか剣呑剣呑した空気のまま終わってしまいました
上司と部下のやり取りが噛み合わず、フロア全体が剣呑剣呑な雰囲気になっていたのを今でも覚えています
「剣呑性」
剣呑性(けんのんせい)とは、物事や状況、人の言動などが不穏で、危険や対立を招きかねない性質・傾向を持っていることを指す言葉です。「剣呑」が一時的な雰囲気や表情を表すのに対し、「剣呑性」はその背景にある構造や本質としての危うさを示します。
そのため、感情の描写よりも、事象の分析や評価を行う文章で用いられることが多く、ビジネス文書や評論、レポートなど、やや硬めの文脈に適しています。直接人に向かって使うよりも、状況や施策、発言内容などを客観的に説明する際に使うと、冷静で説得力のある表現になります。
【例文】
その発言には対立を深めかねない剣呑性があり、慎重な言葉選びが求められると感じた
交渉の進め方に剣呑性が見え始めたため、第三者を交えた調整が必要になった
「剣吞がる」「剣呑さ」
剣呑がるとは、人がある状況や相手に対して、危険そうだ、不穏だと感じて警戒する様子を表に出すことを意味します。「剣呑」が状態そのものを指すのに対し、「剣呑がる」は主観的な反応や態度に焦点が当たる表現です。そのため、誰かの感情や受け止め方を描写する場面で使われます。文章表現としてはやや文語的で、日常会話よりも小説、エッセイ、レポートなどに向いています。
【例文】
新しい取引先の強い口調に、若手社員が少し剣呑がる様子を見せていた
急な方針転換に対し、現場は不安を覚え、全体的に剣呑がる反応を示していた
「剣呑」を正しく理解するための2つのポイント
「剣呑」を正しく理解して使えるようになるために、気を付けておきたい2つのポイントがあります。そのポイントは以下のとおりです。

明らかに危険な時には使わない
「剣呑」を使う際の1つ目のポイントは、明らかに危険な時には使わないことです。例えば、今まさに台風が直撃しており、停電したり川の堤防の決壊によって大洪水が起こってしまったりした場合には使えません。
台風が近づいてきて風が強くなり出したときや、近くの川が氾濫危険水位に近づいているような状況であれば、「剣呑だ」と表現することができます。