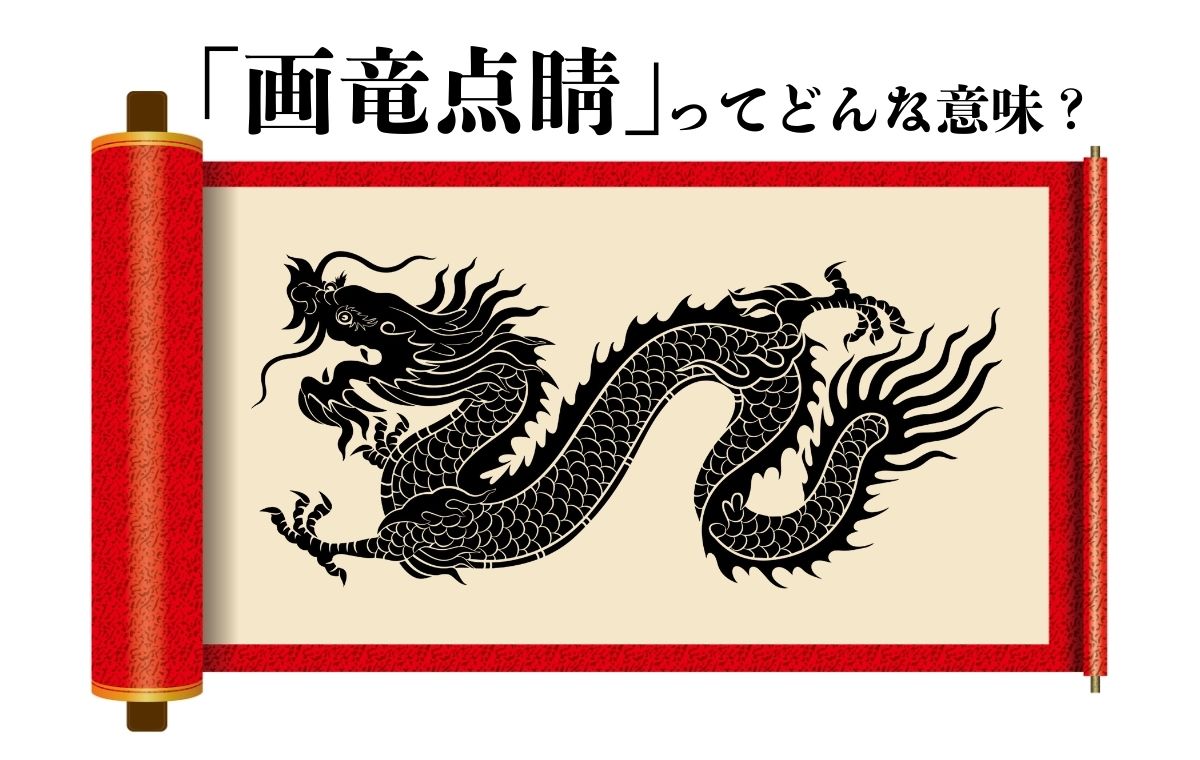正しい読み方は「がりょうてんせい」。「最後の大仕上げ」を意味します。
Summary
- 「画竜点睛」の読みは「がりょうてんせい」で「がりゅうてんせい」は誤りである
- 「最後の大事な仕上げ」や「ほんの少し手を加えることで全体が引き立つこと」を意味する
- 類語には「点睛開眼」(てんせいかいがん)や「肝」(きも)、「入眼」(じゅがん)などがある
Contents
「画竜点睛」の意味や読み方とは?
大学の入試問題にも出題されることがある「画竜点睛」ですが、読みを間違いやすい熟語でもあります。まずは、正しい読み方や意味をチェックしていきましょう。
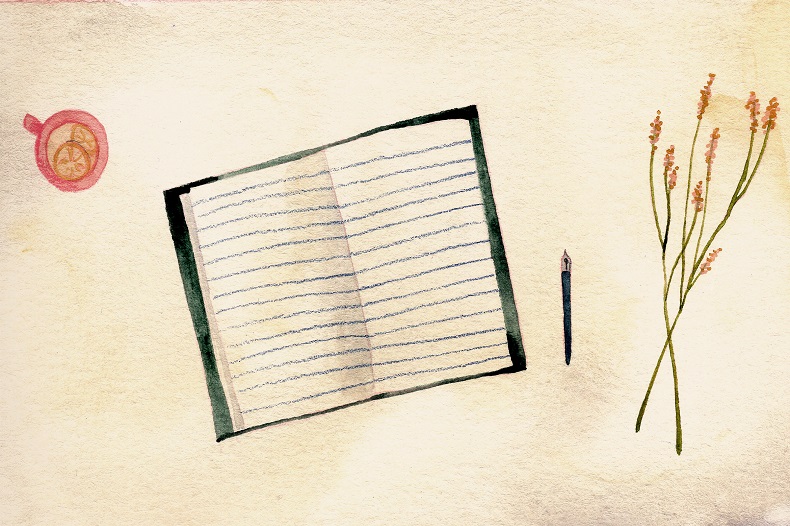
読み方や意味
「画竜点睛」は「がりょうてんせい」と読み、「がりゅうてんせい」と読むのは誤りです。また、4文字目は「晴」でなく「睛」と書きます。読み方と漢字は特に間違いやすいポイントなので注意してください。意味は以下の通りです。
がりょう‐てんせい〔グワリヨウ‐〕【画▽竜点×睛】
最後の大事な仕上げ。また、ほんの少し手を加えることで全体が引き立つこと。
小学館『デジタル大辞泉』より引用
「画竜」は「絵に描かれた龍」のこと、「点睛」は「瞳を描くこと」を意味します。そして、漢字の「睛」には、「瞳」という意味があります。つまり「画竜点睛」とは、「竜の絵に瞳を描き入れること」を表すのです。瞳を描き入れることは絵に表情を与え、魂を吹き込むようなもの。このことから、「最後の大仕上げ」や「少しの手を加えることで、仕上がりがいちだんと良くなること」を表す熟語として使われています。
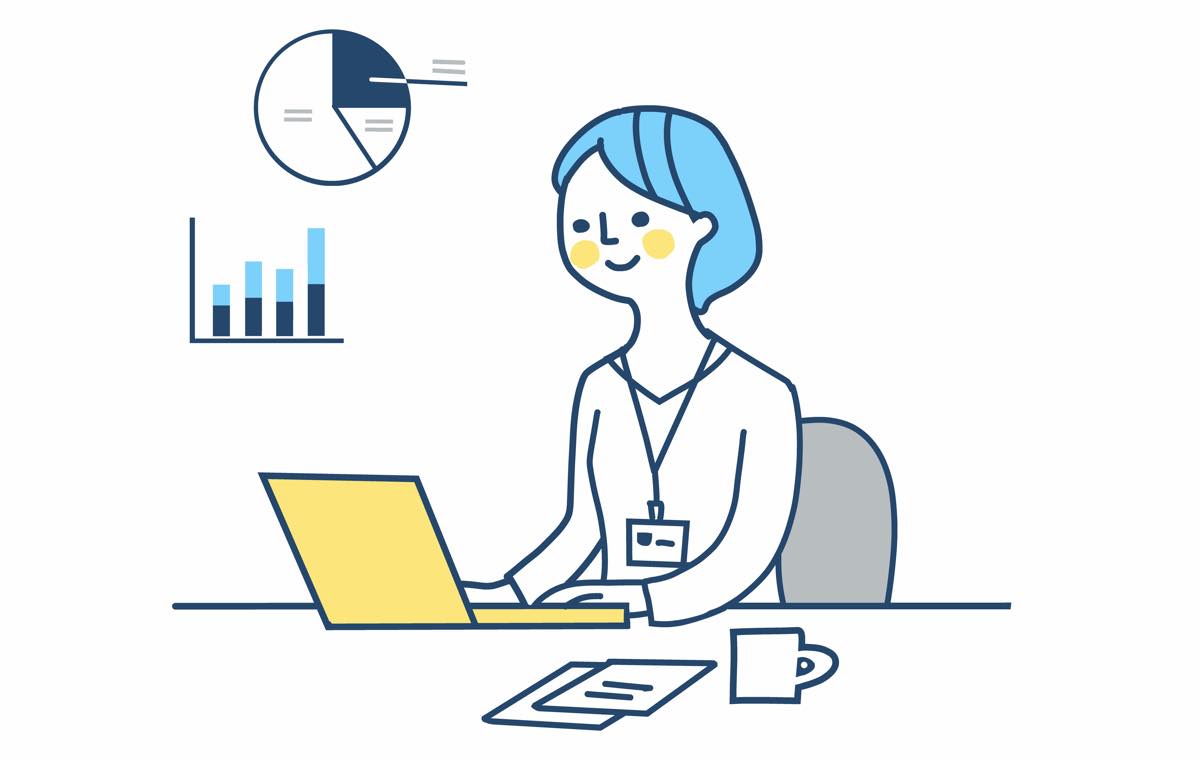
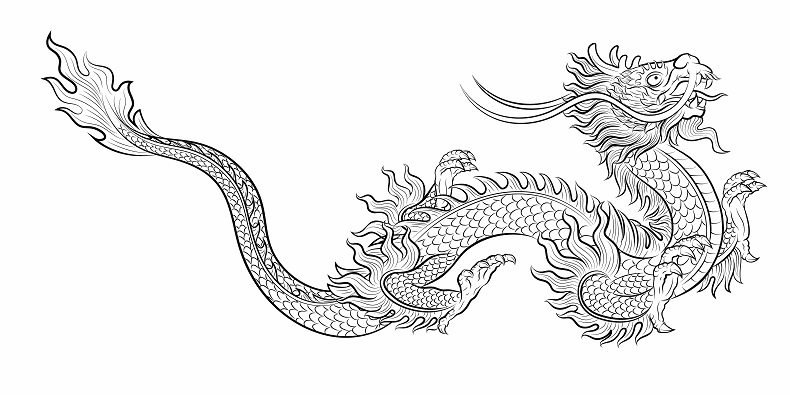
「画竜点睛」の由来とは?
「画竜点睛」は中国の古事成語で、絵画論『歴代名画記』の「点睛即飛去」という一説に由来します。これは、日本語に訳すと「睛を点せば即ち飛び去らん」、すなわち「瞳を描けばすぐに飛び去ってしまう」という意味の文です。
中国南北朝時代。梁(りょう)に、張僧繇(ちょうそうよう)という画家がいました。絵の名人として名高かった張は、ある寺の壁に竜を描くことになり、4つの竜を描きます。とても荘厳な竜の絵でしたが、よく見ると瞳が描かれていません。
そこで、「なぜ瞳がないのか?」と人々が張に聞くと、「瞳を描くと、竜が飛び去ってしまうから」と答えます。しかし、人々はそれを信じず、張に「瞳を描いてほしい」と懇願。張はそれを聞き入れ、2つの竜に瞳を描き入れました。
すると、たちまち瞳が描かれた竜は、壁から飛び去ってしまったのです。寺の壁に残されたのは、瞳が描かれなかった竜のみ。そんな物語から、物事の大切な仕上げを瞳を描き入れることにたとえた、「画竜点睛」という言葉が生まれました。
「画竜点睛」の書き下し文
「画竜点睛」は四字熟語なので書き下し文はありませんが、その由来となった「点睛即飛去」の書き下し文は下記の通りです。
・点睛すれば即ち飛去(てんせいすればすなわちひきょ)す
「画竜点睛」の現代語訳
「画竜点睛」の由来となった「点睛即飛去」の書き下し文の現代語訳も見てみましょう。
・最後に瞳を描き入れると、竜はすぐに飛び去ってしまった
ネガティブな意味合いの「画竜点睛を欠く」
画竜点睛を欠く(がりょうてんせいをかく)は〝物事がほぼ完成しているにもかかわらず、最後のいちばん大切な部分が抜けているために、全体として不完全になってしまう〟というネガティブな意味合いで使われることがあります。これは、「画竜点睛」が持つ「重要な仕上げ」という意味を逆説的に用いた表現です。
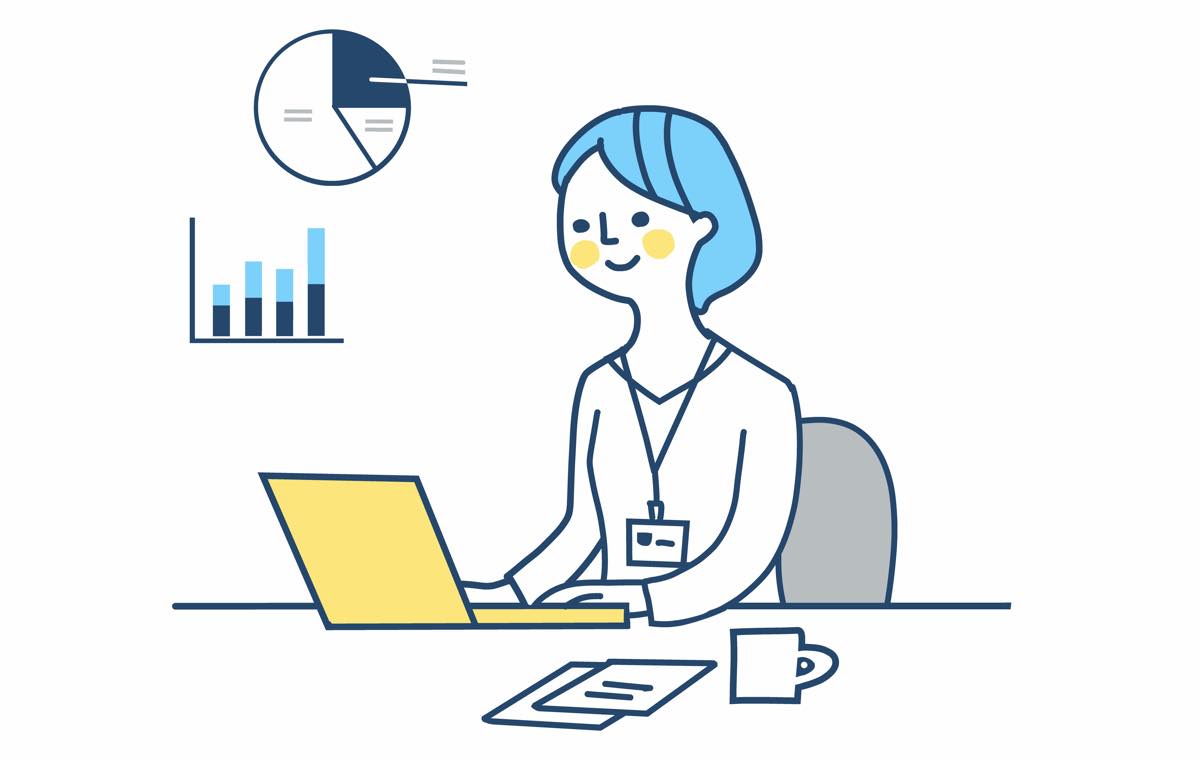
「画竜点睛を欠く」とは、「物事の肝心なところが抜けていること」を表します。
▼あわせて読みたい
【実際の体験談】ビジネスシーンでの「画竜点睛」
ここでは、ビジネスシーンで「画竜点睛」を使った際の成功談や失敗談を紹介していきます。
【episode 1】仕事の最後の詰めを最も重要視するための教訓
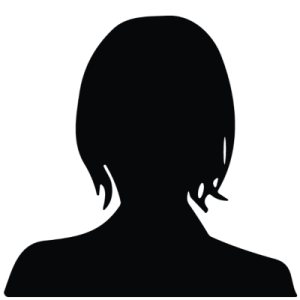
Tさん(46)
若手の頃、ある重要な顧客向けプレゼンの資料作成を任されました。徹夜で作り上げた完璧な資料に自信満々だったのですが、当時の部長は「よくできている。この資料に、我々の強みであるコストメリットを明確な数字で加えることで、まさに画竜点睛となるだろう」とアドバイスをくれました。私は言われた通り、具体的なコスト削減の数字をスライドに加えたところ、プレゼンは大成功。その場で受注が決まったのです。振り返ると部長の言葉は、単に「最後の仕上げをしろ」という意味ではなく、「全体の完成度を完璧にするためには、何が一番重要か」という本質的な問いかけだったんですよね。それ以来、仕事の最後の詰めを最も重要視するようになりました。
【episode 2】誤解を招かないための正確な言葉選びが重要
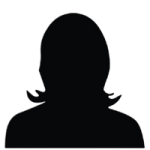
Nさん(48)
私がマネージャーになってから、部下の一人が顧客向けの新サービス説明会を企画しました。企画書は非常によくできており、素晴らしい内容だったのですが、肝心な収益モデルの提示が曖昧で…。そこで私は「この企画は素晴らしいけど、収益モデルがはっきりしない。このままでは画竜点睛となるので、早急に数字を固めてほしい」と伝えました。すると、彼はきょとんとした顔で「え? 最後がいちばんすばらしいってことですか?」と言ったのです。私は自分の言葉の選び方が間違っていたとすぐに気づき、「ごめん。画竜点睛を『欠く』、つまり最後の重要な部分が抜けているから不完全ってこと」と訂正し、言葉の正しい意味を教えました。ビジネスの場で誤解を招かないためにも、正確な言葉選びが重要だと改めて認識させられた出来事でした。
「画竜点睛」の使い方を例文でチェック
続いて「画竜点睛」はどのように使うのか、例文を見ていきましょう。
「せっかく良い作品なのに、見せ方が悪い。まさに画竜点睛を欠くとはこのことだ」
「画竜点睛」の使い方で最も多いのが、先に説明した「画竜点睛を欠く」という表現です。「欠く」は「不足する」や「怠る」という意味。よって「画竜点睛を欠く」とは、「最後の仕上げができていない」というネガティブな意味になり、「詰めが甘い」などというニュアンスで使われます。このフレーズの場合、見せ方が悪いせいで、せっかくの良い作品が台無しになったことを表しています。
「ケアレスミスを防ぐために点睛を意識することが大事だ」
「画竜点睛」の「点睛」だけでも同じ意味で使うことができます。こちらも、最後に仕上げる重要なポイントをいいます。
▼あわせて読みたい
「彼女が優秀なのは画竜点睛を怠らないからだ」
最後まで気を抜かず、物事を成し遂げる人を表現した例文です。これができる人は優秀だといえるでしょう。
「最後に具体的な数字を入れることで、画竜点睛となるだろう」
物事を完璧に仕上げる重要なポイントを指すために、ポジティブな文脈で使う際の例です。
「肝心な価格設定が市場と合っておらず、画竜点睛を欠く状態だ」
物事がほぼ完成しているにもかかわらず、肝心な部分が抜けているために全体として不完全であるというネガティブな意味で使用される例です。
「画竜点睛」の類語や言い換え表現は?
「画竜点睛」の意味や使い方がわかったところで、次は類語や言い換え表現についてみていきましょう。