EXとは?正しい意味を解説
EXは、従業員の満足度や企業の生産性を高めるための重要なアプローチです。EXとはどういう内容か、混同されやすい「従業員エンゲージメント」との違いも説明します。
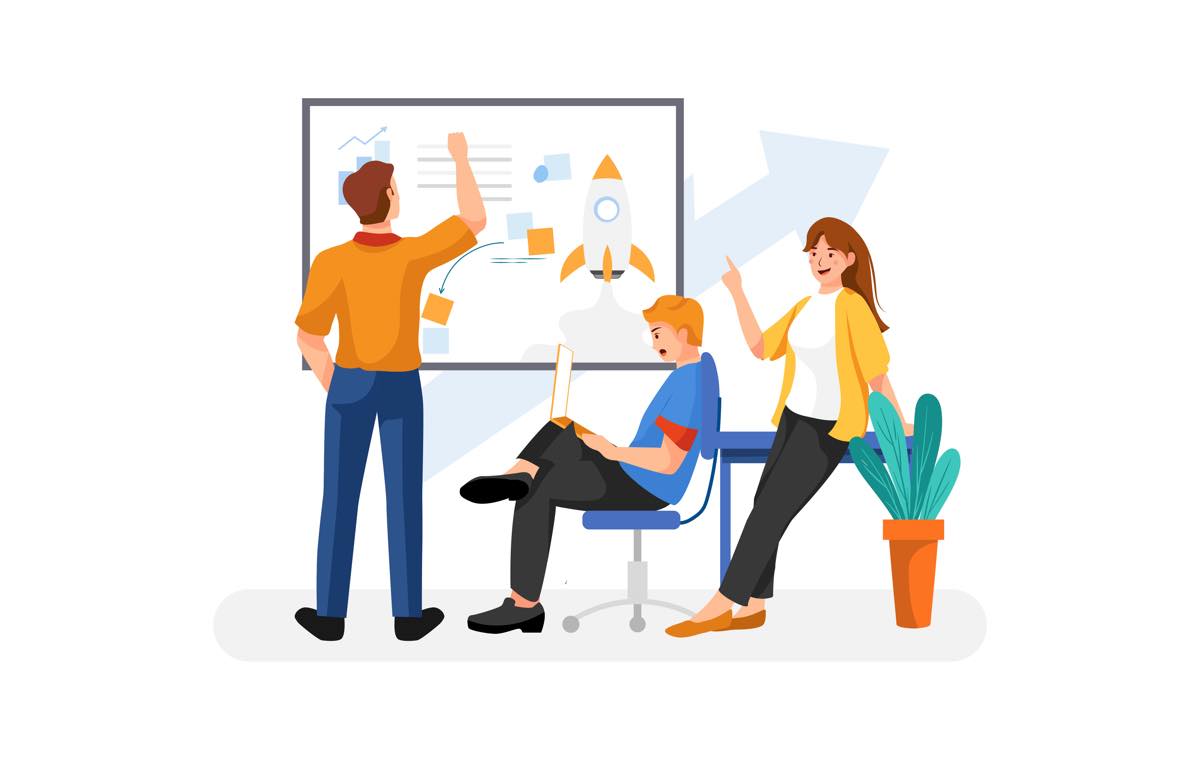
(c) Adobe Stock
日本語では「従業員体験」を指す
Employee Experience(エンプロイー・エクスペリエンス)を略して「EX」と呼び、企業内における従業員体験をいいます。職場環境や福利厚生以外にも、業務内容・成長機会・人間関係など、企業で体験する全てを含むのが特徴といえるでしょう。
エンプロイー【employee】 の解説
雇われている人。雇用人。従業員。
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)エクスペリエンス【experience】 の解説
経験。体験。
引用:『デジタル大辞泉』(小学館)
たとえば商品知識の研修において、単に売上向上を目指すだけでなく、従業員のスキルアップや自信につながる内容を加えれば、従業員のモチベーションアップに期待ができます。
EXは顧客満足度を高めるための「カスタマー・エクスペリエンス」より派生した考え方で、従来の企業目線ではなく、従業員の視点に立ったアプローチに役立つと考えられています。
従業員エンゲージメントとの違い
従業員エンゲージメントとEXの違いは、その範囲にあるといえるでしょう。従業員エンゲージメントはおもに企業への愛着や貢献意欲を指し、生産性や職場定着率の向上などに結びつくものです。
一方、EXはより広い概念といえます。EXは、従業員が企業と関わる全ての体験を含み、業務満足度や成長実感、人間関係に企業文化への共感など、さまざまな要素から成るからです。
従業員エンゲージメントは、EXの積み重ねによる結果の一つともいえるでしょう。Xをうまく活用すれば、従業員エンゲージメントの向上にも期待できるかもしれません。
EXが注目されている理由
EXが注目を集めている背景には、多くの要因が考えられています。労働力不足と働き方改革の推進、人材の流動性の高まり、そしてインターネットやSNSの普及などです。それぞれの要因についてチェックしていきましょう。

(c)AdobeStock
労働力の不足と働き方改革
日本では深刻な少子高齢化により、労働力不足が大きな課題となっています。労働力を確保するためには、働き方の多様化やワークライフバランスを実現できる職場環境が重要です。
長時間の残業や休暇取得の難しさは、従業員満足度の低下や企業イメージの悪化のリスクにもなり得ます。特に、妊娠や子育てをしている社員が働きやすい環境にするには、短時間勤務や産休・育休制度の整備が欠かせません。
定められた時間かつ限られた人数で生産性を維持するためにも、EX活用による従業員エンゲージメント向上が注目されているのです。
人材の動きが流動的になっている
労働力の確保という点では、労働人口の減少だけでなく人材の流動性も大きな問題といえます。現代では、入社から定年退職まで一つの会社に勤めることが当たり前ではなくなったといえるでしょう。最近は、若い世代を中心に転職への抵抗感が薄れつつある傾向もみられます。
このような状況で優秀な人材を確保・定着させるためには、魅力的なEXが重要になってくるでしょう。優秀な人材を求める企業は多いため、金銭的価値だけで引きとどめるのは難しいことも珍しくないようです。
変化の激しい現代社会において、EXの向上は企業の持続的な発展を支える重要な戦略となっています。
企業の情報・内情が簡単に調べられる
インターネットの普及により、企業の労働環境に関わる情報を以前より簡単に調べられるようになりました。
求職者は、企業レビューサイトやSNSを通じて、従業員による生の声にアクセスできます。就職先を決める条件として、給与や福利厚生だけでなく、職場環境や社風を重視する人も珍しくありません。
EXが低ければ、悪い評判が口コミで広がり、企業イメージの低下や労働力不足を招く可能性も。反対に従業員満足度を高めれば、ポジティブな評判を生み出し、人材獲得競争で優位を得ることにつながるかもしれません。
EXを高めるコツ「Employee Journey Map」の作り方
Employee Journey Map(エンプロイージャーニーマップ)は、従業員の視点に立って、入社してから退職するまでの道筋を可視化した表です。EXを高める効果的なツールの作成方法と、3ステップそれぞれのポイントを解説します。

(c)AdobeStock
モデルとなる従業員像を作る
Employee Journey Mapでは、まず社員へのヒアリングを行い、従業員が実際にどのような問題・ニーズを持っているのかを把握します。ヒアリング対象は、できるだけ年齢・性別・職種のバランスが偏らないようにしなければなりません。
従業員の状況が分かったら、その情報を基に典型的な従業員モデルを作成します。ポイントは、外見的特徴や仕事のスキルだけでなく、感情的なパターンやプライベートにおける欲求なども盛り込むことです。より具体的なモデルであるほど、効果的な施策が立てやすくなります。
入社から退職までのフェーズを洗い出す
Employee Journey Mapの2番目のステップは、従業員が体験するフェーズの書き出しです。一般的には、入社・研修期間・配属・業務・育成・評価・退職などに分けて考えます。
フェーズごとに、従業員モデルが抱える課題や悩み、感情や要望を予想して書き込んでいきます。従業員が選びやすい行動やせりふに落とし込むのも、よく使われる手法です。
たとえば、研修期間中の不安や業務遂行時のモチベーション低下、キャリアアップの悩みなどが挙げられます。このように、従業員の感情や課題を具体的に可視化することで、EX向上のチャンスを発見できるでしょう。
分析結果を基にEX向上に向けた対策を立てる
最後に、入社から退職までのフェーズと従業員心理の分析結果から、EX向上へのアクションプランをまとめます。プランを立案する鍵は、フェーズの書き出しで見えてきた改善点です。
たとえば、研修期間中の不安が課題なら、ストレスを軽減する施策が考えられます。モチベーションを維持する対策や、キャリアアップ支援の研修プログラムも効果的でしょう。
また、定期的な従業員アンケートを実施し、各フェーズでの満足度を測定・改善することも大切です。データに基づいた戦略的アプローチにより、持続的な従業員満足度の向上とそれによる企業成長の両立に期待ができます。
EXに注力している企業事例
EXの重要性を理解し、実践している企業もあります。従業員の満足度や生産性を高めている具体的なプランから、EX向上の効果と施策のヒントを探っていきましょう。

(c) Adobe Stock
スターバックス コーヒー
アメリカのスターバックス コーヒーの代表的な取り組みとして、アメリカのアリゾナ州立大学と提携したオンライン学習プログラムがあります。豊富なオンライン学部課程から自由に専攻を選び、学士課程で学べる制度です。
驚くべきは授業料が実質無料という点です。さらに、「学士号を取得していない」「福利厚生の対象である」といった条件を満たせば、雇用形態も問わないようです。
このような取り組みは、従業員のスキルアップやモチベーション向上に貢献しています。結果として顧客満足度の向上や企業成長にもつながっており、まさにEXを重視する経営の好例といえるでしょう。
Netflix
Netflixは、EX向上への独自の取り組みとして、社員の自立した意思決定を促す環境作りに尽力しています。
社内ルールは最小限に抑えられ、従業員は経費の使い方、休暇のタイミングや日数・勤務時間も自己判断に委ねられているようです。ルールはおもに「Netflixの利益のために行動する」という点なのだとか。
この自由度の高い働き方の背景には、従業員へ期待があります。Netflixは優秀な人材を採用し、大きな裁量を与えることで、高い成果を生み出そうとしているのでしょう。
Netflixの取り組みは従来の常識と異なるともいえますが、変化の激しい現代社会で従業員の創造性を引き出す点において、多くの企業にヒントを与えています。
メイン・アイキャッチ画像:(c)AdobeStock
あわせて読みたい

















