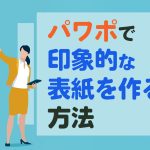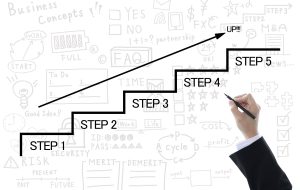「段取り」とは?
「段取り」の言い換え表現を考える前に、まずは段取りがどういう言葉なのかを知っておくことが大切です。言葉の意味を正確に理解すれば、自ずとその言葉の言い換え表現もイメージできるようになるはず。「段取り」の意味を解説します。

(c) Adobe Stock
物事を行う手順や順序を指す言葉
「段取り」は、物事を行う際の手順や順序を指す言葉です。効率的に作業を進めるための計画や準備を意味します。
だん‐どり【段取り】
1 芝居などで、筋の展開や組み立てのしかた。
2 物事を行う順序や手順。また、その準備。「式の段取りをつける」
引用:小学館 デジタル大辞泉
「段取り」は、歌舞伎で使われていた楽屋用語が語源といわれている言葉です。一つのまとまりごとに区切られる話を「段」、芝居の流れのことを「段取り」と称したことが由来とされています。他にも、石段を建設するときに使った言葉を語源とする説もあるようです。
段取りが重要視される場面は、プロジェクト管理・イベント企画・料理の手順・旅行の計画立案など広範囲といえます。たとえば製造業では、生産ラインの効率化に段取りは不可欠でしょう。段取りの重要性を評して「段取り八分、仕事二分」といわれることもあるほど、ビジネスシーンでは段取りが重要視されている傾向にあります。
「段取り」の言い換え表現
「段取り」の言い換え表現を四つ紹介します。言い換え表現をたくさん知っておけば、細かなニュアンスも相手に伝えることができるかもしれません。使う相手や状況に合わせて、適切な表現を使ってみましょう。
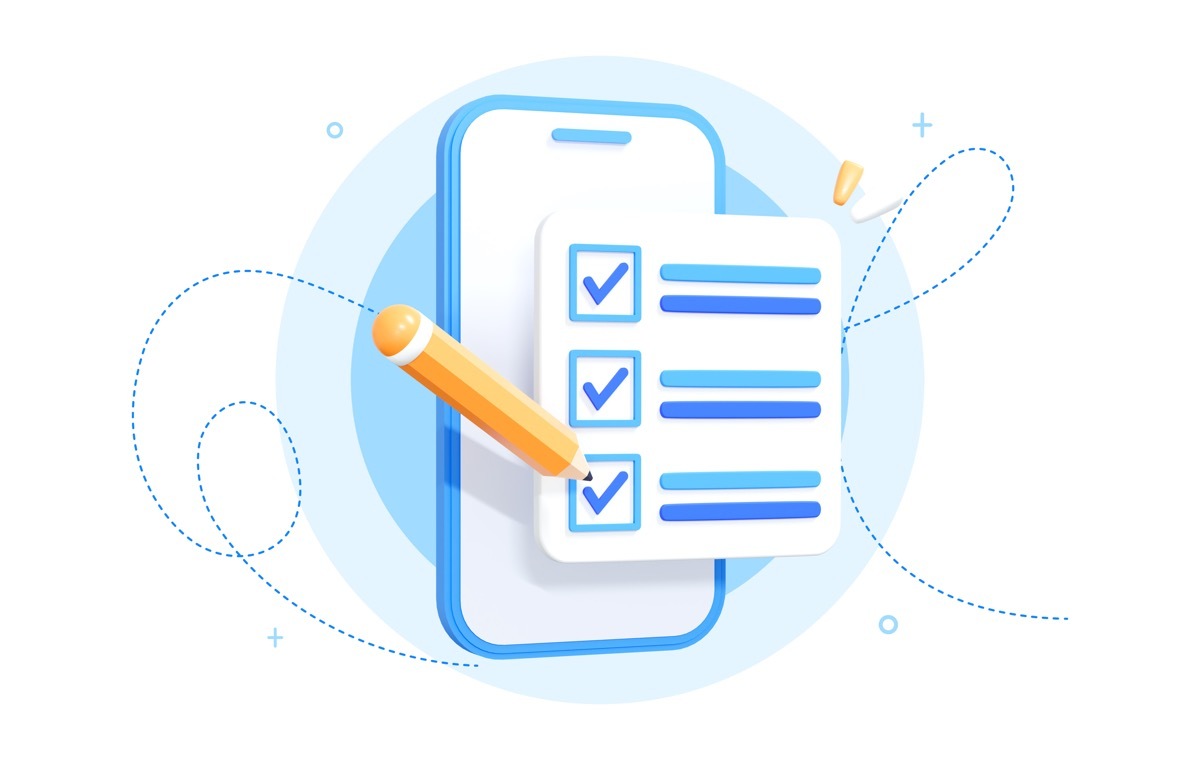
(c) Adobe Stock
「手はず」
「手はず」は、物事を進める前に決めておく順序や手順、または事前に行う準備を意味します。「手はず」を使った例文は以下の通りです。
・明日の会議の手はずは整いましたか?
・会議の前に、資料の準備や会場の手配など、手はずを整えておこう
・旅行の計画は全て手はず通りに進んでいます
シーンを問わない表現ですが、友人との私的な会話では少し堅苦しく感じられる可能性も。ビジネスシーンでは「手はず」、カジュアルな場面では「段取り」というように、TPOに合わせて選択するのがおすすめです。
「ステップ」
「ステップ」は、「段取り」をより具体的に表現する言葉です。物事を進める上での各段階を指し、英語の「step」(日本語に訳せば「歩み」)が語源です。「ステップ」を用いた例文には以下のようなものがあります。
・このプロジェクトは五つのステップで構成されています
・ステップを無視して作業を進めれば、このプロジェクトはきっと破綻するだろう
・プレゼンテーションでは、各ステップを論理的に説明することが重要です
「ステップ」と「段取り」を比べると、「ステップ」はややフランクな印象も受ける表現ともいえるかもしれません。
「準備」
「準備」は「段取り」の本質を表す言葉で、物事を始める前の心構えや必要な作業を指します。「準備」という言葉を使った例文は以下の通りです。
・明日の会議の準備は整いましたか?
・大きなプロジェクトを成功させるには、入念な準備が必要不可欠です
・旅行の準備は万事整ったので、後は今夜ぐっすり寝るだけです
「準備」という言葉は、相手に具体的な行動を想起させるため、タスクの明確化に役立ちます。また「準備不足」という言葉があるように、事前の取り組みの重要性を強調できる言葉ともいえるでしょう。
「工程」
「工程」は製造業や建設業などで多く使われ、仕事・作業の流れや手順、進み具合を示します。「工程」を用いた例文は下記の通りです。
・この製品の製造工程は5段階あります
・ソフトウェア開発において、テストは重要な工程の一つです
・工事の工程表を確認し、スケジュール通りに進んでいるか確認しましょう
ビジネスシーンでは、「工程」という言葉を使うことで、より専門的で体系的な印象を与えられます。一方で、日常会話では少し硬い印象を与える可能性があるため、場面に応じて「段取り」と使い分けるのがおすすめです。
段取りを良くするメリット
「段取りが良くなると何となく仕事が進めやすそう」というイメージを持っている人は多いかもしれません。しかし、実際にどのようなメリットがあるのか、具体的に考えたことがある人は少ないのではないでしょうか。段取りの向上がもたらすメリットを考えていきます。

(c) Adobe Stock
遅延やトラブルを防げる
段取りがスムーズになると、遅延やトラブルを未然に防ぐことに期待ができます。事前に手順や必要な資源を整理することにより、潜在的な問題点を洗い出し、対策を講じられるからです。
たとえば、プロジェクトの各工程に必要な時間を見積もり、余裕を持ったスケジュールを組むことで、予期せぬ事態にも対応しやすくなるでしょう。また必要な機材や人員を事前に確保することで、作業の中断を避けられるかもしれません。
イベント企画では、会場の下見や備品のチェックを事前に行うことで、当日のトラブルを最小限に抑えることに期待できます。このように適切な段取りは、スムーズな進行を支え、結果として時間とコストの無駄を省くことにつながるのです。
生産性が向上する
適切な段取りは、生産性の向上に大きく貢献する取り組みといえます。
たとえば製造ラインでは、工程の最適化により効率が大幅に上がる可能性があります。各工程に適切な量の作業を割り振り、作業時間を均一になるよう調整することで、製造ラインにおける生産性の向上に期待できるでしょう。
また、オフィスワークでも会議の事前準備を徹底することで、議論の質が向上し、意思決定のスピードが加速するかもしれません。たとえば必要な資料を事前に共有しておけば、会議の参加者は前もって自分の意見を整理できるため、会議のスタート後すぐに議論に集中できると考えられます。
このように、適切な段取りはさまざまな場面で生産性を高める鍵となり得るのです。
段取り力を上げるには
実際に、「自分も段取り力を上げたい」と思った人もいるかもしれません。ここでは、段取り力を向上させるためのポイントを解説します。段取り力はちょっとした工夫で高められるので、実践できるものからチャレンジしてみましょう。

(c) Adobe Stock
目的や目標を明確にする
段取りを効果的に進めるには、目的や目標を明確にすることが重要です。目的や目標をはっきりさせることで、ゴールに辿り着くまでに必要な作業や手順が可視化されます。また、目標達成までの進捗も把握しやすくなるため、必要に応じて計画の修正も行いやすくなるでしょう。
目的や目標を決める際に活躍するのが「SMART原則」です。「SMART原則」とは目標の作り方を示した法則のことで、「Specific:具体的」「Measurable:計測可能、数字化できる」「Achievable:達成可能な」「Relevant:関連性」「Time-bound:期限が明確」の五つの要素を踏まえて目的や目標を設定することで、いち早く成功に近づけるとされています。

(c)AdobeStock
「SMART原則」を活用すれば、たとえば「売上を上げる」という漠然とした目標ではなく「3か月以内に新規顧客を10社獲得して売上を15%増加させる」というような具体的な目標を掲げられます。
優先順位を決めて計画を立てる
優先順位を決めて計画を立てることは、段取りの要です。優先順位を決めてから実際の仕事に取り掛からないと、優先すべきタスクを後回しにしてしまい、理想的な段取りを組めない可能性も。
計画を立てる際は、まず目標達成に必要な作業を洗い出し、重要度と緊急度を考慮してリスト化します。次に、各作業にかかる時間を見積もり、全体のスケジュールを組み立てます。
スケジュールを立てる際は、予期せぬ事態に備えて余裕を持たせることが大切です。スケジュールに余裕がないと、万が一トラブルが起こった際に遅れを回収できず、結果的に遅延が発生してしまうかもしれません。
事前にシミュレーションをする
事前にシミュレーションを行うことは、段取りを成功させる重要な手法です。実際の動きをイメージしながら手順を確認することで、見落としがちな細部まで把握できるでしょう。
たとえばプレゼンテーションの準備では、本番を想定して行う練習を録音して聞き直すことで、話の流れや説明の分かりやすさなどを改善できます。スムーズに進行できなかった部分や、聞いていて分かりにくい部分を修正すれば、より説得力のあるプレゼンが完成するはずです。
このようなシミュレーションを通じて得られた気付きを段取りの微調整に生かすことで、本番での余裕が生まれ、突発的な事態にも柔軟に対応できるようになります。
メイン・アイキャッチ画像:(c)AdobeStock
▼あわせて読みたい