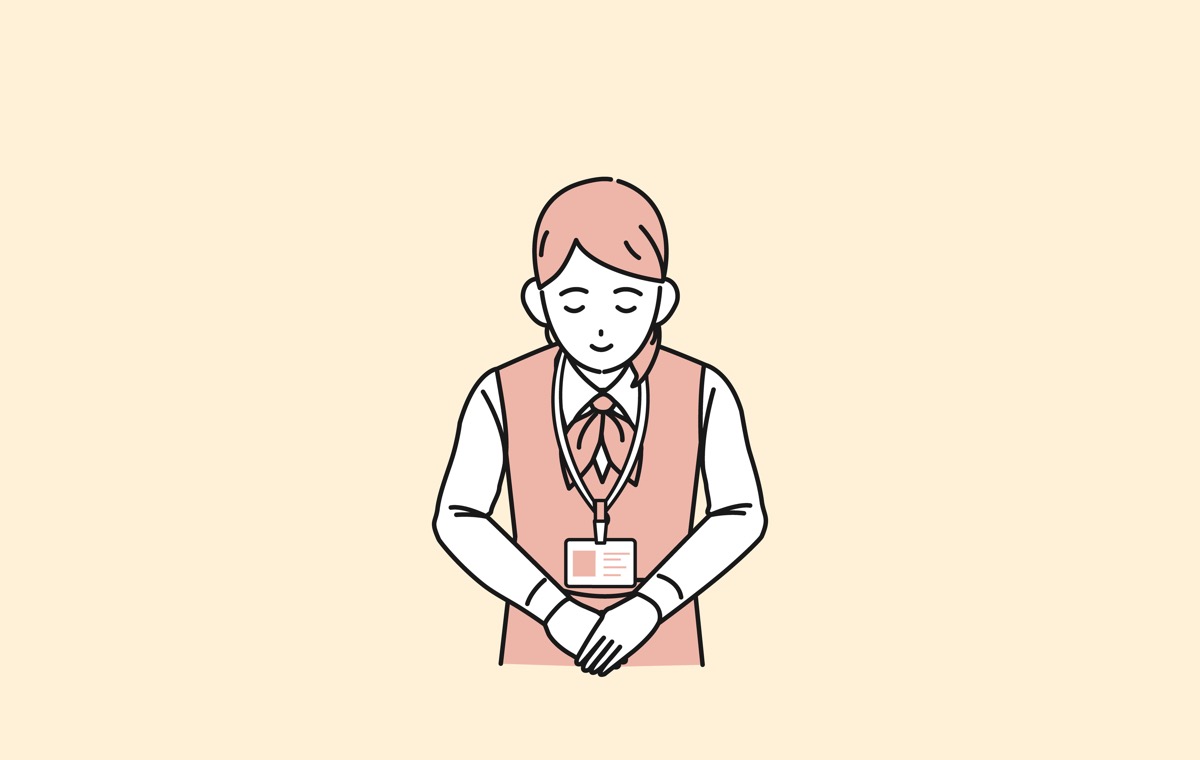「善処します」は、「状況に合わせて、適切に対処します」「できるかぎり対応します」という表現です。
Summary
- 「善処します」とは、「状況に合わせて、適切に対処します」「できるかぎり対応します」という意味
- 明言を避けた表現のため、相手からは「曖昧な返答」と受け取られる可能性があるので注意
- 確実に対応する場合は、「承知いたしました」「~に対応いたします」などの表現を使いましょう
Contents
ビジネスシーンで時折使われる、「善処します」というフレーズ。あなたは、実際に使ったことがありますか? 丁寧に聞こえる言葉ではありますが、使うシーンを誤るとかえって失礼に当たることも…。本記事で、「善処します」の意味や類語、注意点を解説しますので、正しい使い方をしっかり押さえてみてくださいね。
「善処」の意味や読み方とは?
まずは、「善処」の読み方と意味からチェックしていきましょう。
「善処」とは
読み方は「ぜんしょ」。意味を辞書で確認してみましょう。
ぜん‐しょ【善処】
[名](スル)
1. 適切に処置すること。「事情に応じて―する」
2. (「善所」とも書く)仏語。来世に生まれるべきよい場所。人界・天上・諸仏の浄土など。「後生(ごしょう)―」
『デジタル大辞泉』(小学館)より引用
さらに分解して、それぞれの漢字の意味を詳しく見ていきます。「善」の意味は、「物事にうまく対処する」「行いや性質などが好ましい」。「処」は、「とりはからう」「物事がうまく運ぶように対処する」という意味です。つまり、「善処します」とは「状況に合わせて、適切に対処します」表現なのです。
ポジティブな印象を持たれるかもしれませんが、「できるかぎり対応します」「前向きに検討します」という曖昧なニュアンスを含む表現でもあります。
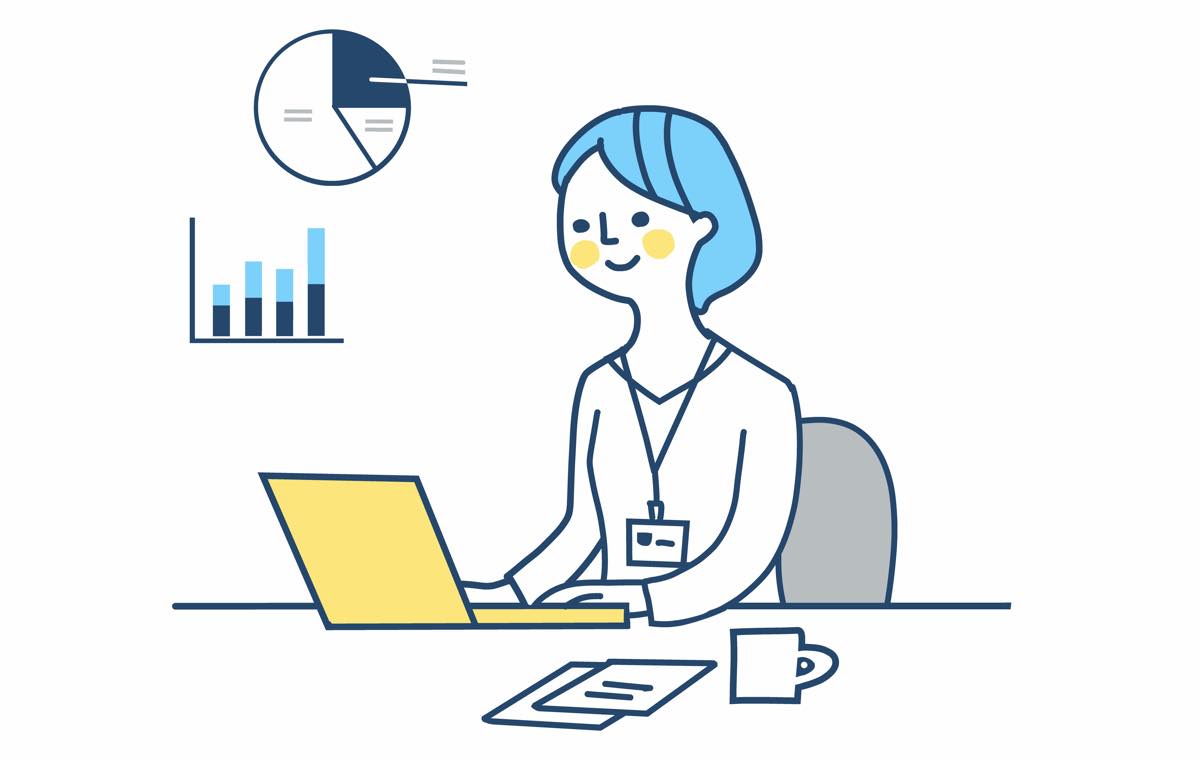
▼あわせて読みたい

(c) Adobe Stock
ビジネス等で使う時の注意点
「善処」の意味を把握したら、続いては使う場面などの注意点を見ていきましょう。
返事としては曖昧
「善処します」は依頼などの返事として使うことができる言葉ですが、上記でも述べたように「できる限り対応します」といったような、明言を避けた表現です。そのため、相手からは「曖昧な返答」と受け取られる可能性があります。
したがって、確実に対応する場合、「善処します」という言葉はふさわしくありません。その場合は、「承知いたしました」「~に対応いたします」などと答えたほうがいいでしょう。
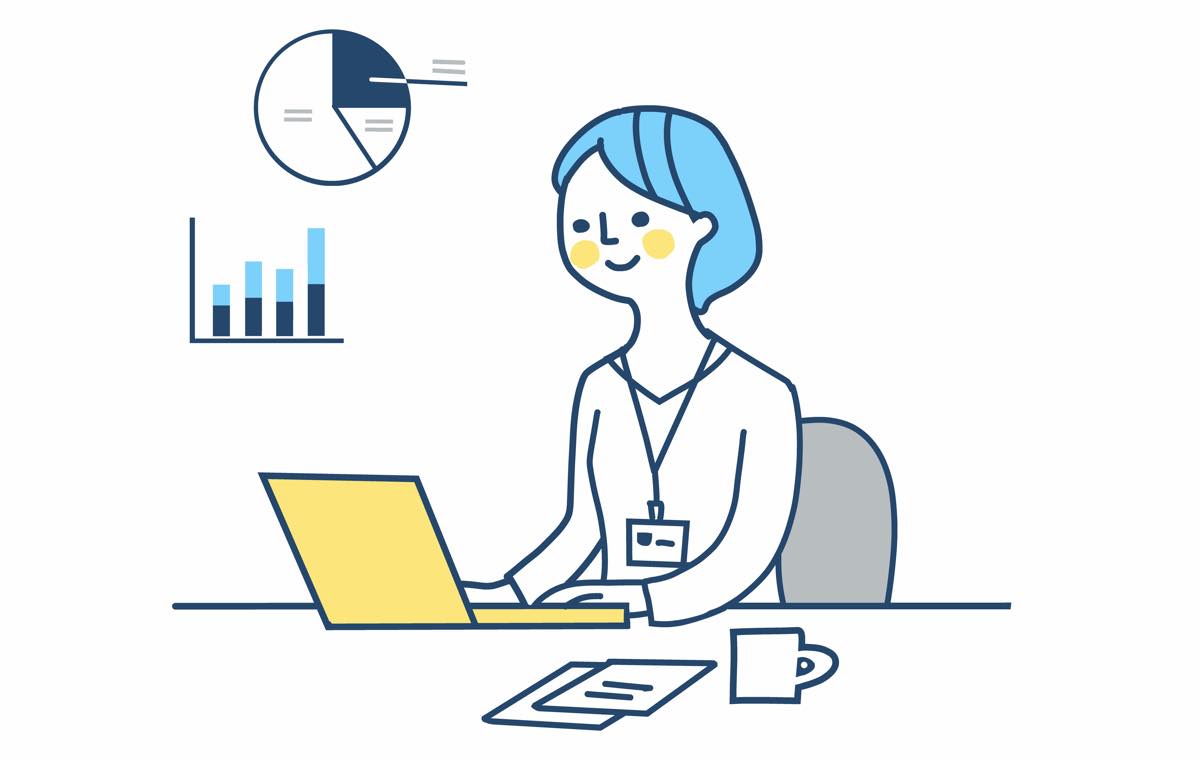
確実に対応する場合は、「承知いたしました」「~に対応いたします」などの表現を使いましょう。
目上の方への使い方
「善処」自体は敬語表現ではありません。「善処」+「します(丁寧語)」とすることで、はじめて目上の方にも使える敬語表現となります。さらに丁寧な表現にするならば「善処いたします」です。
また、目上の方や取引先の相手に「善処」をお願いする場合は、「ご善処」という表現が好ましいでしょう。「ご善処のほど、よろしくお願い申し上げます」とすると丁寧に伝えることができます。
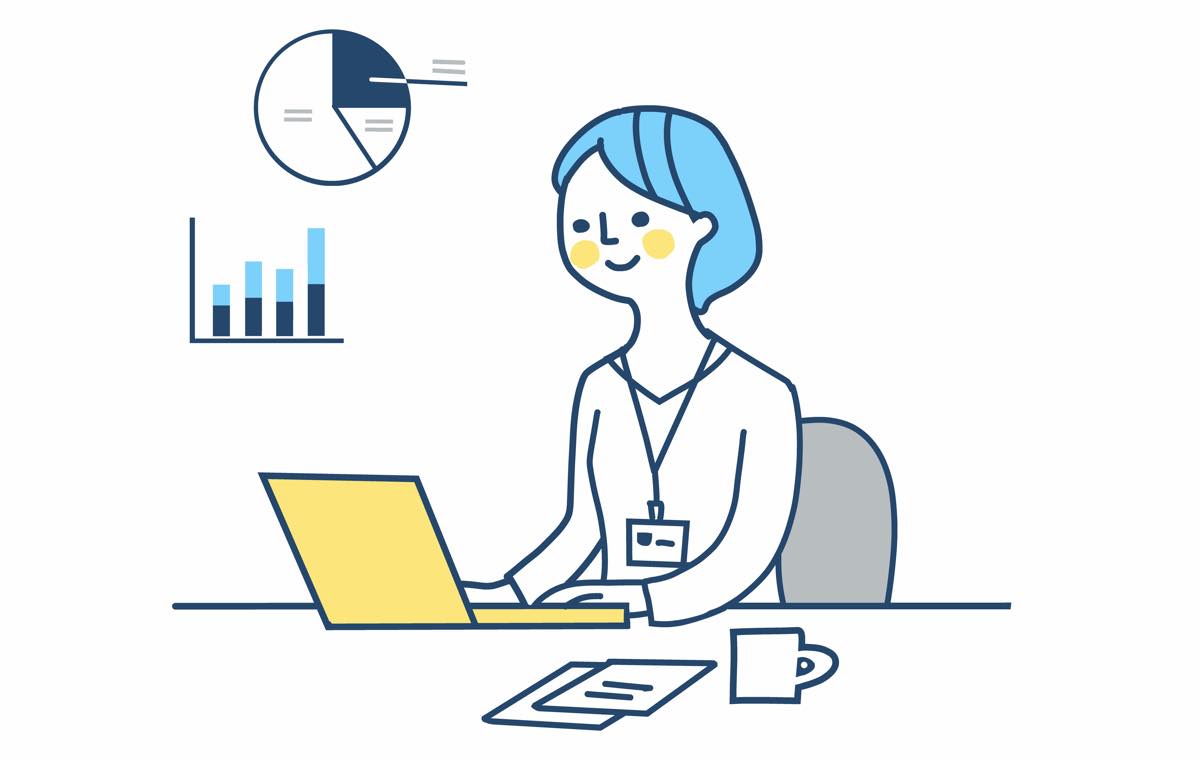
目上の方へは、「善処します」や「善処いたします」と表現し、こちらからお願いしたい場合には「ご善処のほど、よろしくお願い申し上げます」と伝えましょう。
「適切に善処します」は二重表現
二重表現とは、同じ意味の言葉を重ねて使う誤った表現のことです。たとえば「頭痛が痛い」、「馬から落馬」といった具合です。「適切に善処します」は、「適切に」が「善処」の意味合いと重なり、二重表現となります。
使い方を例文でチェック
「善処します」は一般的に、依頼への返答や、こちらから適切な対応をお願いする際などに用いられます。以下、例文で使い方を紹介していきます。
「善処します」
例文
・その件につきましては、善処します
依頼を受けて、「その件は、できる限り対応いたします」という意味。「Yes・No」などの断定的な表現を避けた〝一旦保留〟というニュアンスを含んだ表現であり、すぐに返事ができないことに対して使う言い回しです。このような返答をした場合は曖昧なままにせず、後日ハッキリとした返事をする必要があります。
「善処いたしますが」
例文
・善処いたしますが、ご期待に添えない場合はご容赦ください
こちらのフレーズは、「できるかぎりの対応はしますが、期待に添えない場合はお許しください」という意味。依頼に対して、「できないかもしれません」という旨を事前に断っておく表現です。「ご容赦ください」とあらかじめ謝罪の言葉を添えることで、相手に低姿勢な印象で伝えることができるでしょう。
▼あわせて読みたい