「鏡開き」はいつ? その由来は!?
鏡開きとは、お正月に歳神様(としがみさま)が滞在していた「依り代(よりしろ=居場所)」であるお餅を食べることで、霊力を分けてもらい、1年の良運を願う行事。地域によって多少違いはあるものの、一般的には毎年、1月11日に行います。
門松や鏡餅は神様をお迎えするためのもので、歳神様が家々に滞在する期間は「松の内」と言われています。松の内が過ぎて歳神様をお見送りしたら、鏡餅を食べ、1年の無病息災を願うという流れ。
お正月中、飾っていたお餅は固くなっているので、包丁で切る方もいるかもしれませんが、実はこれ、NGなんです! そこで今回は鏡開きのルールについて、マナーコンサルタントの西出ひろ子さんにお話を伺いました。

刃物で「切る」のはNG! 木槌や金槌で叩いて割るのが正解
「鏡餅は、縁起の良い食べ物として、『切る』を連想させる、包丁などの刃物で『切る』ことは避けるとされています。また、神様が宿っていた鏡餅に刃物を向けることは行わないという理由から切ることはしないという配慮も。鏡餅を分け与えるときなどは、木槌や金槌で少しづつ叩きながら最後に勢いよく叩いて開く(割る)とされています」(西出さん)
ちなみに、「鏡割り」ではなく「鏡開き」と呼ぶのは、「開く」が末広がりで縁起が良く、お正月にぴったりの言葉だからだそうです。
お餅をどうやって食べている? おすすめの食べ方
鏡開きをしたら、そのお餅はどう味わうのがおすすめ? お気に入りのお餅の食べ方を、Domaniと姉妹メディアOggiの読者に聞いてみました。圧倒的に多いのは「砂糖醤油」「きな粉」「磯部」でしたが、ほかにも気になる食べ方が続々!

「レンチンでバター醤油」(みなこさん/会社員)
「トロトロにレンジで加熱してピーナッツバターを使ってピーナッツ餅にする」(taeko.0610314さん/契約社員・派遣社員)
「ちょっと小さく切ってシチューに入れる」(もいたんさん/会社員)
「ほうれん草の胡麻和えにお餅をからめます」(のっそりぐまさん/公務員)
「ひきわり納豆と大根おろしを混ぜたものを餅と食べたり、チョコレートシロップがけ餅にしたりします」(natsuko28123さん/自営業)
「チーズを挟んで海苔を巻いて食べる 」(izuさん/会社員)
「すりごまと豆腐と砂糖を混ぜてもちとからめる」(ききららさん/パート・アルバイト・フリーター)
「炊き込みご飯に入れる」(ゆかいんさん/契約社員・派遣社員)
「お餅とクリームソース、とろけるチーズで、餅グラタンにしています」(もこもこさん/自営業)
「ネギを3本4本切って豚肉と炒めてその上に餅を置いて蒸す。3分くらいして餅が柔らかくなったら醤油を豪快にたらして食べます。最高にネギも豚肉も餅もおいしいです」(ぼんぼやーじゅさん/自営業)
「明太子とモチで〝もちーじょ(アヒージョ)〟にしています。鍋に入れてもおいしい」(みさっきさん/会社員)
お正月、おせちやお餅はやっぱり食べたい! でもお餅は同じ食べ方だと飽きてしまうということもありますが、読者の皆さんおすすめのレシピ、ぜひ試してみてくださいね。
アンケート調査 対象:Oggi、Domaniのメルマガ会員SNSフォロワーなど。小学館IDアンケートフォームによる回答 回答数:670 期間:2023年11月15日〜25日
マナーコンサルタント
西出ひろ子
参議院議員秘書を経て政治経済ジャーナリストの秘書を経験。その後 マナー講師として独立渡英し海外で起業した経験もあるため、グローバルな視点からマナーをわかりやすく解説している。その実績や成果は、テレビや雑誌などでもマナー界のカリスマとして多数紹介されており、「マナーの賢人」として「ソロモン流」(テレビ東京)や「スーパーJチャンネル」(テレビ朝日)などのドキュメンタリー番組でも紹介された。基本のマナーとそこに気くばりを加えたワンランク上のマナーを紹介した新刊、『さりげないのに品がある気くばり美人のきほん』が好評発売中!
『さりげないのに品がある気くばり美人のきほん』
西出ひろ子マナーサロンHP
イラスト/村澤綾香 構成/木戸恵子 再構成/Domani編集部
あわせて読みたい
-
 目上の方への年賀状に「迎春」「賀正」はNG!【年末年始にやってはいけな…
目上の方への年賀状に「迎春」「賀正」はNG!【年末年始にやってはいけな… -
 お正月に食べてはいけない「肉」があるって知ってた?【年末年始にやって…
お正月に食べてはいけない「肉」があるって知ってた?【年末年始にやって… -
 上司のお子さんにお年玉をあげてもいい?【年末年始にやってはいけないこ…
上司のお子さんにお年玉をあげてもいい?【年末年始にやってはいけないこ… -
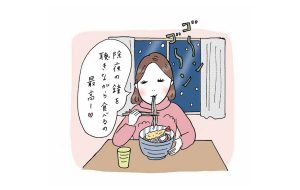 「年越しそば」には食べてはいけない時間帯がある!?【年末年始にやっては…
「年越しそば」には食べてはいけない時間帯がある!?【年末年始にやっては… -
 元日に「朝風呂」は入ってはいけない理由【年末年始にやってはいけないこ…
元日に「朝風呂」は入ってはいけない理由【年末年始にやってはいけないこ… -
 遅すぎる初詣はNG? 何日までに行くのが正解?【年末年始にやってはいけな…
遅すぎる初詣はNG? 何日までに行くのが正解?【年末年始にやってはいけな… -
 おせち料理の品数、偶数にしてはいけないって知ってた!?【年末年始にやっ…
おせち料理の品数、偶数にしてはいけないって知ってた!?【年末年始にやっ… -
 銀行窓口が閉まってる! お年玉は新札を用意しなきゃダメ?【年末年始にや…
銀行窓口が閉まってる! お年玉は新札を用意しなきゃダメ?【年末年始にや… -
 去年の「正月飾り」を使い回してもいい?【年末年始にやってはいけないこ…
去年の「正月飾り」を使い回してもいい?【年末年始にやってはいけないこ… -
 駆け込みNG!大晦日に掃除をしてはいけないって本当?【年末年始にやって…
駆け込みNG!大晦日に掃除をしてはいけないって本当?【年末年始にやって…








