「〜て頂きたく」という表現は、ビジネスシーンで頻繁に用いられる言葉です。しかし、適切な使い方を深く理解している人は意外と少ないかもしれません。この表現を正しく使うことは、単なる礼儀作法以上に、信頼や敬意を形にすることでもあります。
そこでこの記事では、「〜て頂きたく」の使い方のポイントを掘り下げて解説していきます。
「〜て頂きたく」の意味と表記の仕方
まずは、「〜て頂きたく」の正しい意味と使い方を確認していきましょう。

(c) Adobe Stock
「〜て頂きたく」の意味は?
「〜て頂きたく」は、「自分のために何かをしてもらう」意味を持つ謙譲表現で、補助動詞です。
まず、文法的にこの表現を分解してみましょう。「〜」の部分には動詞の連用形が入り、それに接続助詞「て」が続きます。ここに補助動詞「頂く」が加わり、最後に希望の意味の助動詞「たい」の連用形「たく」が接続して、話し手の希望を表す形になっています。
補助動詞としての「頂く」の意味を辞書でも確認しましょう。
いただ・く【頂く/▽戴く】
8(補助動詞)
(ア)(動詞の連用形に接続助詞「て」を添えた形に付いて)話し手または動作の受け手にとって恩恵となる行為を他者から受ける意を表す。「これが先生にほめて―・いた作品です」「せっかく来て―・いたのですが、主人は今おりません」「一言声をかけて―・いたらよろしかったのに」
(イ)(接頭語「お」または「御(ご)」に動詞の連用形またはサ変動詞の語幹を添えた形に付いて)8(ア)に同じ。「これから先生にお話し―・きます」「お読み―・きたい」「御心配―・きまして」「御審議―・きたい」
(ウ)(動詞の未然形に使役の助動詞「せる」「させる」の連用形、接続助詞「て」を添えた形に付いて)自己がある動作をするのを、他人に許してもらう意を表す。「させてもらう」の謙譲語。「あとで読ませて―・きます」「本日は休業させて―・きます」引用『デジタル大辞泉』(小学館)より8補助動詞の意味を抜粋
辞書の定義を見ても、「頂く」という補助動詞は、話し手に恩恵をもたらす行為を他者から受ける意味を持っていることがわかります。例えば、「ご確認していただきたく存じます」という表現には、相手が行動を起こすことで話し手に恩恵があると同時に、それをお願いする際のへりくだった姿勢が込められています。
「〜て頂きたく」と「〜ていただきたく」、どちらが正しい?
結論からいうと、「〜て頂きたく」と「〜ていただきたく」、どちらも正しいといえます。
文化庁の「新しい『公用文作成の要領』に向けて(報告)」では、「動詞・形容詞などの補助的な用法では仮名で書く」と記されていますが、これはあくまでも原則。「〜ていただきたく」の方が望ましいですが、「〜て頂きたく」と書いても誤りではありません。
『日本国語大辞典』(小学館)の補助動詞としての用法説明の中にある例文でも、「可哀さうだとか、不憫(ふびん)だとか、思ってさへ頂(イタダ)けば」(人情本『春色恋廼染分解』)が掲載されているように、漢字で表記されています。
「〜て頂きたく」の誤った使い方|二重敬語に注意
「〜て頂きたく」は謙譲語だと先述しました。ですから「〜て頂きたく」を使うときは、二重敬語(同じ種類の敬語を重ねて使うこと)にならないよう注意が必要です。以下では、誤用例と改善案を紹介します。

(c) Adobe Stock
誤用例と改善案
誤用例1:「拝見させて頂きたく存じます」
「拝見」自体が謙譲語のため、「頂きたく」は不要です。
改善案:「拝見したく存じます」
誤用例2:「お伺いさせていただきたく存じます」
「お〜する」も謙譲語であるため、簡潔にする方が自然です。
改善案:「伺いたく存じます」
簡潔で的確な表現を心がけ、過剰な敬語表現にならないよう、気をつけましょう。
ビジネスシーンでの「〜て頂きたく」の具体例
「〜て頂きたく」は相手への敬意や配慮を示す言葉として多用されています。このセクションでは、具体例を通じて実務での応用法を詳しく見ていきましょう。
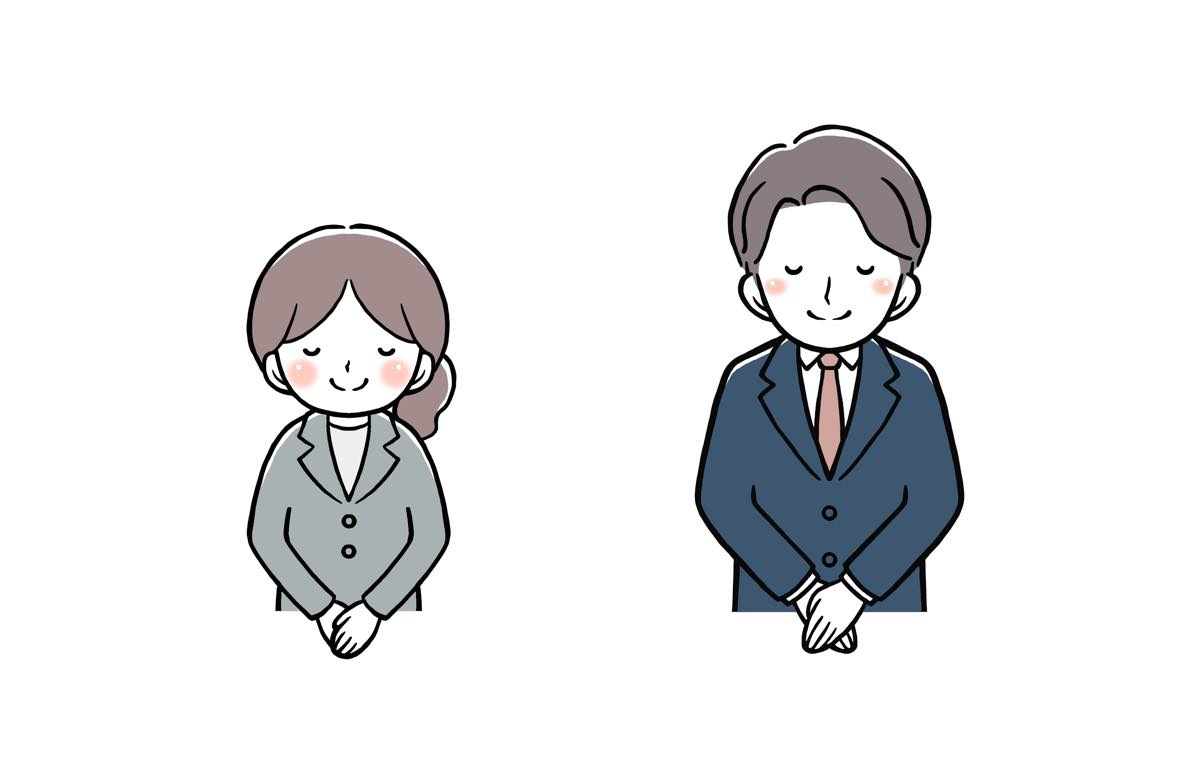
(c) Adobe Stock
依頼文の例:「ご確認して頂きたく存じます」
資料送付時のメールでは、ただ「確認してください」と伝えるのではなく、「ご確認して頂きたく存じます」と表現することで、相手の時間や労力に対する配慮を示すことができます。
こうした言葉遣いは、依頼内容を明確にし、相手に不快感を与えない信頼関係構築のための一助となりますよ。
案内文の例:「ご来場して頂きたくお願い申し上げます」
「お願い申し上げます」と組み合わせることで、行動を促しながらも、相手の都合に配慮するニュアンスがあります。顧客や取引先への依頼文は、特に丁寧な配慮が必要です。
最後に
「〜て頂きたく」という表現を正確に使いこなすことは、管理職としてのコミュニケーションスキルの高さを示す一つの指標といえるかもしれません。日々の業務において、丁寧な言葉遣いを活用することは、信頼関係の強化やスムーズな協力体制の構築に寄与するといっても過言ではないでしょう。この記事が、読者の皆さまにとって新たな気づきや学びの機会となれば幸いです。
TOP画像/(c) Adobe Stock
関連リンク












