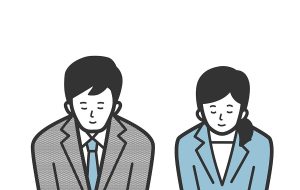ビジネスで「了解しました」は失礼?
「了解しました」はよく使われる表現ですが、ビジネスマナーとしては失礼とされるケースも。「了解しました」の意味を解説した上で、なぜビジネスシーンで失礼とされることもあるのか、どのような背景で失礼と捉えられ得るのかを押さえておきましょう。
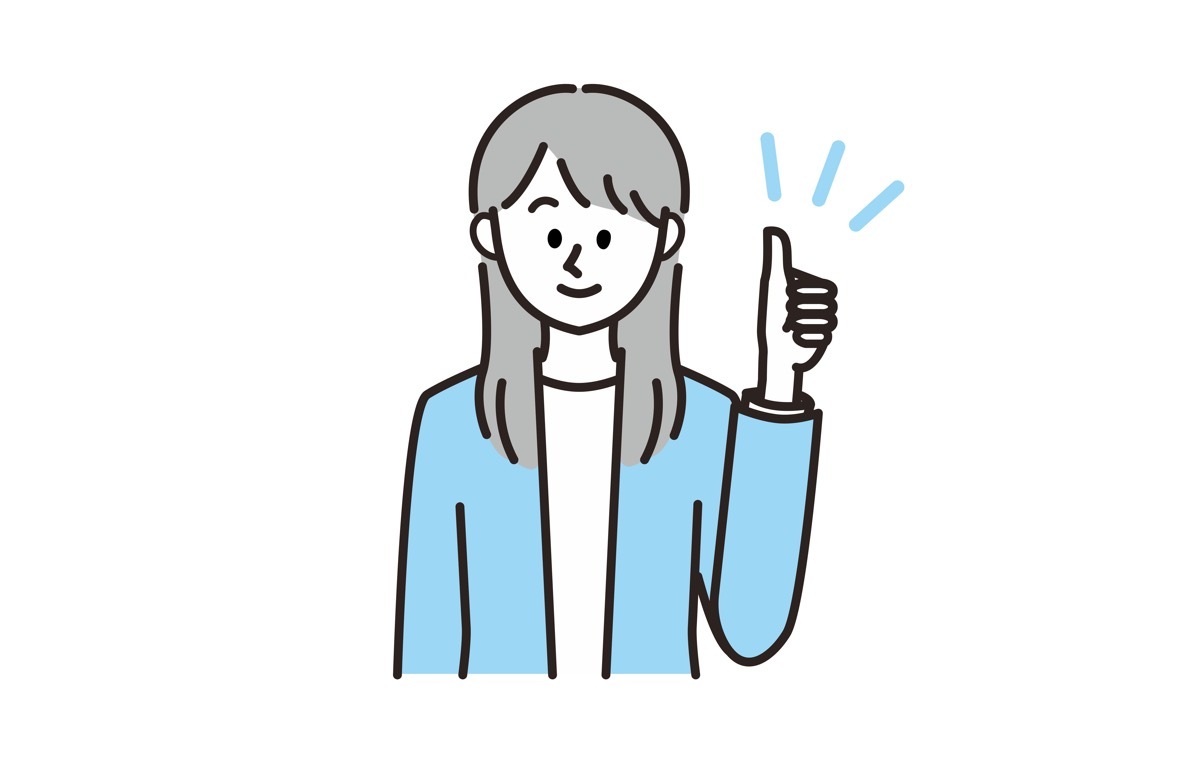
(c) Adobe Stock
「了解しました」の意味と基本的な使い方
「了解」は辞書によると、以下のように説明されています。
[名](スル)
1 物事の内容や事情を理解して承認すること。了承。「—が成り立つ」「来信の内容を—する」
(中略)
引用:小学館 デジタル大辞泉
「了解」という言葉そのものに相手を上げたりへりくだったりする意味合いはありません。しかし「しました」によって丁寧語になっているため、敬語としては成立しているといえるでしょう。
「了解しました」が失礼とされる理由は?
「了解しました」は敬語としては成立しているものの、相手によっては失礼と捉えられる可能性も考えられるため、注意が必要です。上司・取引先への「了解」は、軍隊用語由来というイメージから「命令口調」「上から目線」と受け取られるケースも。
ただし、明確に「失礼である」という根拠はありません。イメージの問題なので、相手が失礼だと感じる可能性が高い関係性・場面では、避けた方が賢明だと考えるとよいでしょう。
「了解しました」が失礼ではない・失礼になる場面
ビジネスシーンでの「了解しました」は、使う場面や相手との関係性によって印象が変わるといえるかもしれません。失礼に感じられにくいケース・避けた方が無難なケースを具体的にまとめました。

(c)AdobeStock
同僚・後輩やカジュアルなチャットではOKなケースも
同僚や後輩相手なら、仕事上節度のある敬語を使っていれば問題ないでしょう。「了解しました」は丁寧語のため、同僚・後輩相手には特に気を使わずに使えるといえます。
また、Slackなどのチャットではフランクさが好まれる面があり、従来のビジネスシーンではNGとされてきた「了解です」「OKです」などの略語が使われる場合も。むしろ丁寧な表現を避け、簡潔な表現にすることで業務の効率化につながる場合があるかもしれません。
目上相手でも、社内文化や相手との距離感によっては許容される例は少なくないでしょう。自社が慣習を重んじる文化なのか、フランクにやりとりしてよい文化なのかを見極めた上で使い分けると安心です。
上司や取引先など目上に使うのは避けた方が無難
「了解しました」は、辞書的な意味においては目上に対して失礼な言葉ではありませんが、ビジネスメールや社外への正式な文章では避けられる傾向が見られます。特に相手がどのようなコミュニケーションを好むかが分からない場合は、より丁寧と捉えられる表現の方がベターでしょう。
社外での「了解しました」は原則避ける、社内の目上に対する「了解しました」は相手が敬語にこだわるかどうかを見極めた上で、使用の可否を判断しましょう。
実際の職場ではどう使われている?
「了解」には歴史的に見ても失礼な要素はないとする学者もおり、実際にビジネスの現場で使われてきました。一方で「了解」が目上に対して失礼だとしているマナー本やビジネスマナー系サイトの記事も散見されます。
敬語の常識は時代とともに変わるもの。「了解しました」も場面や相手に合わせて、使うのが適切かどうかを判断することが大切です。どうしても迷ってしまう場合は、より丁寧に聞こえる類似表現を使うとよいでしょう。
「了解しました」が失礼になるときに使える類語・言い換え
「了解しました」がふさわしくないと感じたとき、代わりにどのような表現を使うべきか悩む人も多いでしょう。よく使われる類似表現とそのニュアンスを比較し、どのような場面で使うとよいかを整理していきます。

(c) Adobe Stock
目上への使用も安心「承知しました」
「承知」は辞書によると、以下のような意味を持つとされています。
[名](スル)
1 事情などを知ること。また、知っていること。わかっていること。「無理を—でお願いする」「君の言うことなど百も—だ」「事の経緯を—しておきたい」
2 依頼・要求などを聞き入れること。承諾。「申し出の件、確かに—した」
3 相手の事情などを理解して許すこと。多く下に打消しの語を伴って用いる。「この次からは—しないぞ」
引用:小学館 デジタル大辞泉
「了解」と同じく言葉自体に謙譲語や尊敬語の意味合いはありませんが、多くの人が目上に使っても問題ないと考える傾向にあるため、言い換えに使えるといえます。「承知しました」はあらゆるビジネスシーンで無難に使える表現なので、語彙のレパートリーとして取り入れておくとよいでしょう。
堅すぎない点も「承知しました」が使いやすいポイントです。「する」の謙譲語「いたす」を使って、「承知いたしました」とすればより丁寧になります。
より丁寧な「かしこまりました」
「かしこまりました」は「承知しました」より丁寧な表現です。「かしこまる」は、辞書によると以下のように定義されています。
[動ラ五(四)]
(中略)
3 命令・依頼などを謹んで承る意を表す。承りました。「はい、—・りました」
引用:小学館 デジタル大辞泉
動詞自体に「命令や依頼を謹んで引き受ける」という謙譲語の意味合いが含まれるため、「かしこまりました」はとても丁寧な言い回しです。取引先や目上の方に対しても使用して差し支えありません。
ただ、上司とメール・チャットでやりとりする際に使うより、接客業などでお客さまに使う方が適しているかもしれません。距離を置く必要のある相手・初対面の相手には、好印象を与えやすいでしょう。
「了解しました」と類語の使い分け一覧
「了解しました」と紹介してきた類似表現は、表で使い分けを覚えておくと便利です。一覧表で見てみましょう。
| 表現 | 使うのに向いている相手 | 備考 |
|---|---|---|
| 了解しました | 同僚や部下・距離感の近い上司 | フランクに捉えられることが多い。目上には注意が必要 |
| 承知しました | 上司や取引先 | 無難で丁寧な表現。事務的な印象になることも |
| かしこまりました | お客さまや初対面の相手 | フォーマルで丁寧だが、日常的に使うにはやや堅すぎることも |
「使える相手」は関係性や社風・やりとりに使うツールの特色などによっても変わるため、あくまで一般的な目安と考えてください。
「了解しました」や類語を使う際のポイント
「了解しました」は場合によっては失礼に捉えられ得る表現ですが、類語を使ったり感じよく伝える工夫をしたりすることで印象が変わります。了解しましたを使うときの印象をよくする具体例や、場面別(メール・チャット・対面)のOK・NG表現も押さえておきましょう。

(c)AdobeStock
「了解しました」や類語の印象をよくする一言アレンジ例
「了解しました」を使うときは、単体で使うよりも後に感謝や配慮の言葉・今後の自分の意思を加えると好印象に。「かしこまりました」「承知しました(いたしました)」も同様です。いくつか例文を見てみましょう。
【例文】
・了解しました。日程を調整いただき、ありがとうございます。
・かしこまりました。◯日までに確認の上、ご連絡いたします。
・承知いたしました。何かあれば、お気軽にご連絡くださいませ。
ただ「了解しました」と言うよりも、感謝の言葉を添えることで、より丁寧な印象を与えられることが分かります。
メール・チャット・対面でのシーン別NG/OK表現集
敬語の適切な使い方は、社風や関係性によっても変わります。ただ、一般的にNGとされる表現や推奨される表現は場面別に覚えておいた方が便利でしょう。
【メールでのNG/OK表現例】
・NG:了解しました。よろしくです。(カジュアルすぎる)
・OK:承知しました。ご対応のほど、よろしくお願いいたします。
【チャットでのOK表現例】
「了解ですー」
※社内チャット・同僚や部下相手ならOK
【対面でのOK表現例】
「かしこまりました。すぐに対応いたします」
※フォーマルな第一印象を大切にしたいときにおすすめ
挙げたのはあくまで一例ですが、今後のビジネスシーンでのやりとりに活用してみてください。
まとめ
-
「了解しました」は使い方によっては失礼とされるが、社風や相手との関係性によって許容されるケースも多い
-
目上の相手や社外メールには「承知しました」や「かしこまりました」の方が無難
-
表現を一言アレンジしたり、類語と使い分けるコツを押さえたりすることで、自信を持ってビジネス上のコミュニケーションができる
「了解しました」を使ってよいのか悩んでいた場合は、紹介してきた使い分けの基準を覚えておきましょう。目上に対しても失礼と捉えられない表現をマスターしておくことで、ビジネスシーンでの印象がグッとよくなるはずです。
メイン・アイキャッチ画像:(c)AdobeStock
TEXT
Domani編集部
Domaniは1997年に小学館から創刊された30代・40代キャリア女性に向けたファッション雑誌。タイトルはイタリア語で「明日」を意味し、同じくイタリア語で「今日」を表す姉妹誌『Oggi』とともに働く女性を応援するコンテンツを発信している。現在 Domaniはデジタルメディアに特化し、「働くママ」に向けた「明日」も楽しむライフスタイルをWEBサイトとSNSで展開。働く自分、家族と過ごす自分、その境目がないほどに忙しい毎日を送るワーキングマザーたちが、効率良くおしゃれも美容も仕事も楽しみ、子供との時間をハッピーに過ごすための多様な情報を、発信力のある個性豊かな人気ママモデルや読者モデル、ファッションのみならずライフスタイルやビジネス・デジタルスキルにも関心が高いエディターたちを通して発信中。
WEB Domani
あわせて読みたい