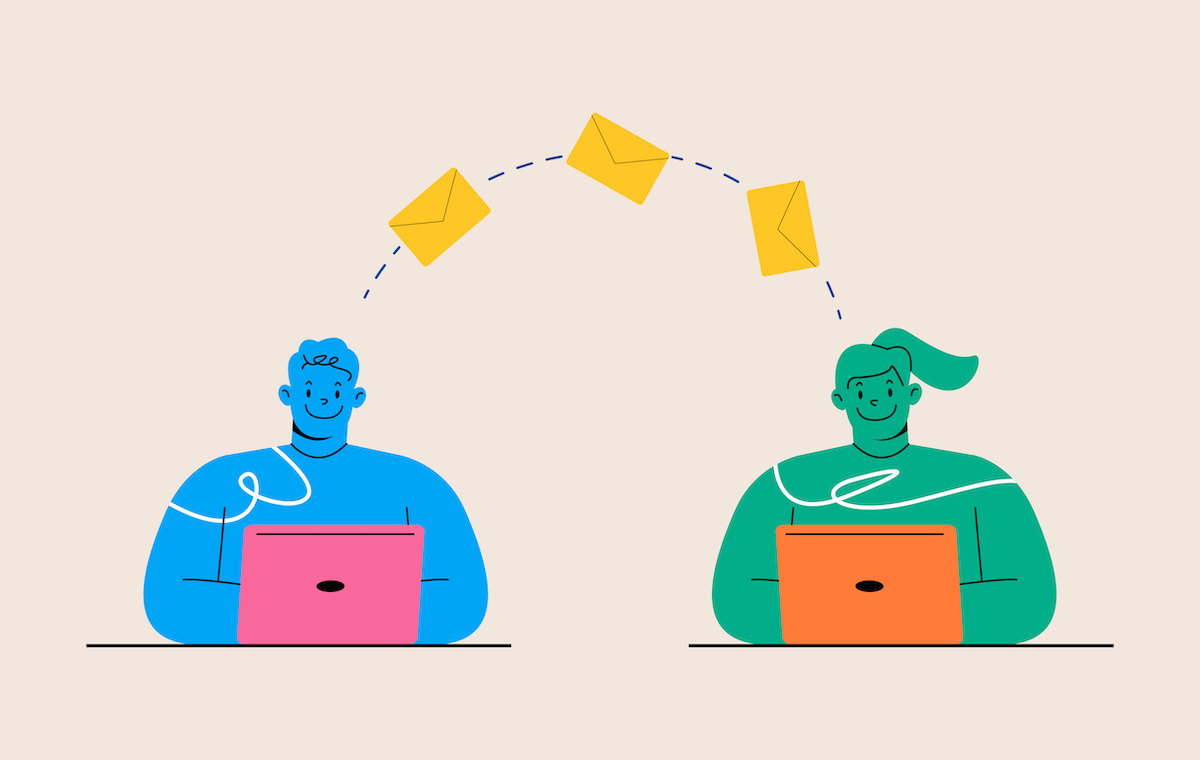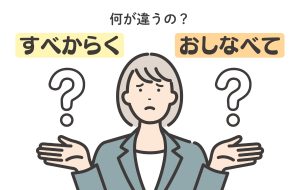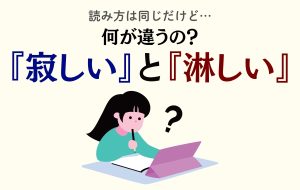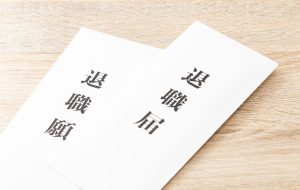ただ、「了解です」は「了解」に続くべきは「する」であり、「です」は本来誤った使い方です。よほど砕けたチャットでのやりとりを除き、ビジネスの場では避けるのがよいでしょう。
Contents
【目次】
ビジネスで使う「かしこまりました」と「承知いたしました」の違いとは?
「かしこまりました」「承知いたしました」はどちらも丁寧な印象を与える表現です。しかし、ビジネスでの使い分けに戸惑う人も多いかもしれません。まずは意味や共通点を押さえた上で、それぞれのニュアンスの違いを解説します。

(c)Adobe Stock
基本の意味と共通点をおさらい
「かしこまりました」「承知いたしました」は、ともに「(命令や依頼について)了承した」ことを丁寧に伝える表現です。どちらも尊敬語(※)ではなく、謙譲語(自分の行為をへりくだって相手に対する敬意を表す)に当たります。
丁寧に敬意を表しながら、了承の意を伝える表現であることが「かしこまりました」「承知いたしました」の共通点です。ただし、両者のニュアンスには若干の違いがあるため、ビジネスシーンでは使い分けるとよいでしょう。
※相手や話の登場人物の動作・状態を高めてその人に対する敬意を表す種類の敬語
「かしこまりました」のニュアンスと使い方
「かしこまる」は辞書によると、以下のような意味です。
(中略)
3 命令・依頼などを謹んで承る意を表す。承りました。「はい、—・りました」
出典:小学館 デジタル大辞泉
「かしこまる」という単語自体が、へりくだる意味合いを持つことが分かります。さらに「〜した」の丁寧語「ました」も付いており、目上にも使える非常に丁寧な表現です。
書き言葉よりも話し言葉で使う方が一般的とされますが、ビジネスメールなどで「接客的な丁重さ」を強調したい場合には文面でも用いられることがあります。
「承知いたしました」のニュアンスと使い方
「承知」の意味は、辞書で次のように解説されています。
[名](スル)
1 事情などを知ること。また、知っていること。わかっていること。「無理を—でお願いする」「君の言うことなど百も—だ」「事の経緯を—しておきたい」
2 依頼・要求などを聞き入れること。承諾。「申し出の件、確かに—した」
(中略)
出典:小学館 デジタル大辞泉
上記の解説からも分かるように、「承知」自体にへりくだる意味合いはありません。しかし、「する」の謙譲語「いたす」を使って「承知いたしました」とすることで、「承知いたしました」はへりくだる表現になっているといえます。
丁寧であり、目上に対しても使って問題ない表現です。ただし「承知いたしました」には、「かしこまりました」と違って「事情を理解している」という意味合いがあるといえます。
「承知=理解と了承」、「かしこまる=命令をへりくだって受け入れる態度」と考えると分かりやすいでしょう。「承知いたしました」は話し言葉・書き言葉どちらでも使えますが、文章で使う方が一般的です。
「かしこまりました」「承知いたしました」を使い分けるコツ
「かしこまりました」「承知いたしました」は意味が近い表現ですが、使うシーンや相手によって印象が変わることも。迷ったときの判断基準を持つことで、言葉選びに自信が持てるようになるはずです。

(c)Adobe Stock
相手との関係性で選ぶ
社外の取引先や目上の相手へのメールでは、事情を理解しているという意味合いを持つ「承知いたしました」の方が適しているといえるでしょう。「かしこまりました」でも間違いではありませんが、中には口語的と捉える人も。
接客的な応対(店舗や窓口・電話など口頭のやりとり)では、「かしこまりました」の方が丁寧な印象でしょう。社内やフラットな関係では、文脈次第でどちらでも問題ありません。
相手との関係性や社風・やりとりに使うツールによっては、よりカジュアルな表現も許容される場合があります。
場面ごとの適切な使い分け
「かしこまりました」と「承知いたしました」は、大筋の意味に違いはないと考えて問題ないでしょう。ただ、事情の理解を含む、へりくだって命令を受け入れるというニュアンスの違いがあるため、場面によって使い分けることをおすすめします。
例
・対面・電話:丁寧かつ柔らかく聞こえる「かしこまりました」
・メール・報告書:理解したという意味合いを持つ「承知いたしました」
特に時間変更や納期・業務連絡など、「内容を理解している」ことが伝わった方がよいメールへの返信には、「承知いたしました」が向いているでしょう。
「かしこまりました」「承知いたしました」の使い分けが分かる例文
言葉の違いを知識として理解していても、具体的な例を知らないと実際の場面で使い分けにくいでしょう。シーン別の例文を確認することで、具体的なイメージを持ちやすくなります。

(c)AdobeStock
※ここでは一般的な認識から話し言葉に「かしこまりました」、書き言葉に「承知いたしました」を使っていますが、本来どちらも口語・文語どちらに使って問題ない言葉です。
「かしこまりました」の電話・対面での使用例
電話や対面で「かしこまりました」を使う際は、以下の例文を参考にしてみましょう。
【アポイントの変更連絡を受けた場面の例文(電話)】
・クライアント:
「○月○日14時の打ち合わせですが、急遽別の予定が入りまして、15時からに変更いただけますでしょうか?」
・自社担当:
「15時からに変更ですね。かしこまりました。それでは、改めて○月○日15時にお待ちしております。」
内容の理解を示す言い換えを先に添えることで、「かしこまりました」でも内容をしっかり分かっていることが伝わります。電話の場合、「ですね」といった柔らかい語尾を使うのもおすすめです。
【来客対応・受付業務で受け答えをするときの例文(対面)】
・来客者:
「本日14時に予約していた株式会社○○の山田と申します。担当の方にお取り次ぎいただけますか?」
・受付担当:
「お待ちしておりました、山田様。かしこまりました。担当を呼んでまいりますので、こちらで少々お待ちいただけますでしょうか。」
「かしこまりました」の直後に状況説明や依頼された内容に対応する意図を加えると、機械的にならず、接客にふさわしい柔らかな応対になります。
「承知いたしました」のメールでの使用例
「承知いたしました」はメールでよく使う表現なので、テンプレートとして文章の構造を覚えておくと便利です。
【クライアントからの依頼に対する返信の例文(メール)】
件名:◯月◯日ご依頼の件について株式会社○○
営業部 ○○様
いつも大変お世話になっております。△△株式会社の□□です。
ご連絡いただきました件、承知いたしました。
資料につきましては、○月○日中を目安にご用意いたします。
何かご不明な点などございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
「承知いたしました」を一文で終わらせず、具体的な対応内容を続けて記載することで、実務的な信頼感が一層増すでしょう。「お気軽にお申し付けくださいませ」といった柔らかい締めの表現も、印象を和らげるポイントです。
【上司からの依頼に対する返信の例文(メール)】
件名:会議資料の作成について
○○部長
お疲れ様です。総務課の□□です。
会議資料作成の件、承知いたしました。
本日中にドラフトをまとめ、明朝までにご確認いただけるよう手配いたします。
ご希望の形式などございましたら、あらかじめお知らせいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
上司への返信でも、「承知いたしました」は丁寧で適切な表現といえます。対応の予定や確認依頼を添えることで、報連相が行き届いた印象になります。「〜いただけますと幸いです」といった控えめな依頼表現も、好印象につながるでしょう。
「かしこまりました」「承知いたしました」と類似表現の使い分け
「かしこまりました」「承知いたしました」の使い分けが分かっても、実際のビジネスではさらに多様な表現を求められることもあるでしょう。類似表現を知っておくと、語彙の幅が広がり応対にも余裕が生まれるかもしれません。
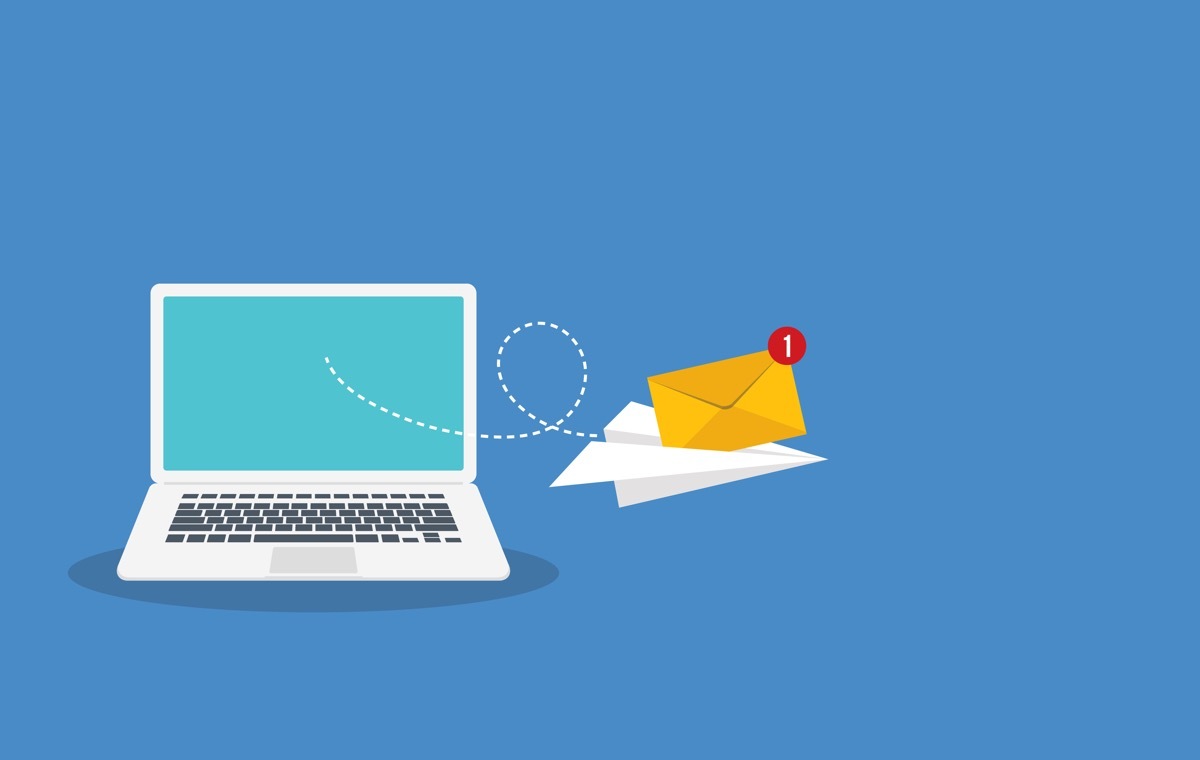
(c) Adobe Stock
よりカジュアルな表現「了解しました」
「了解」は辞書で、以下のように解説されています。
[名](スル)
1 物事の内容や事情を理解して承認すること。了承。「—が成り立つ」「来信の内容を—する」
(中略)
出典:小学館 デジタル大辞泉
この解説が示す通り、「了解」自体には尊敬語・謙譲語の意味はありません。「しました」も丁寧語ではありますが、「いたしました」と異なり謙譲の意味を持たない表現です。
そのため「了解しました」は単に「話の内容を理解して受け入れた」ことを伝える言葉といえます。「いたしました」とすれば文法的には謙譲語になりますが、相手によっては「軽い印象」や「上から目線」と受け取られる可能性もあるかもしれません。
特に取引先や初対面の相手に「了解しました」と返事をするのは、避けた方が無難でしょう。社内チャットや同僚・部下とのやりとりであれば、丁寧語ではあるため問題ないケースが大半のようです。
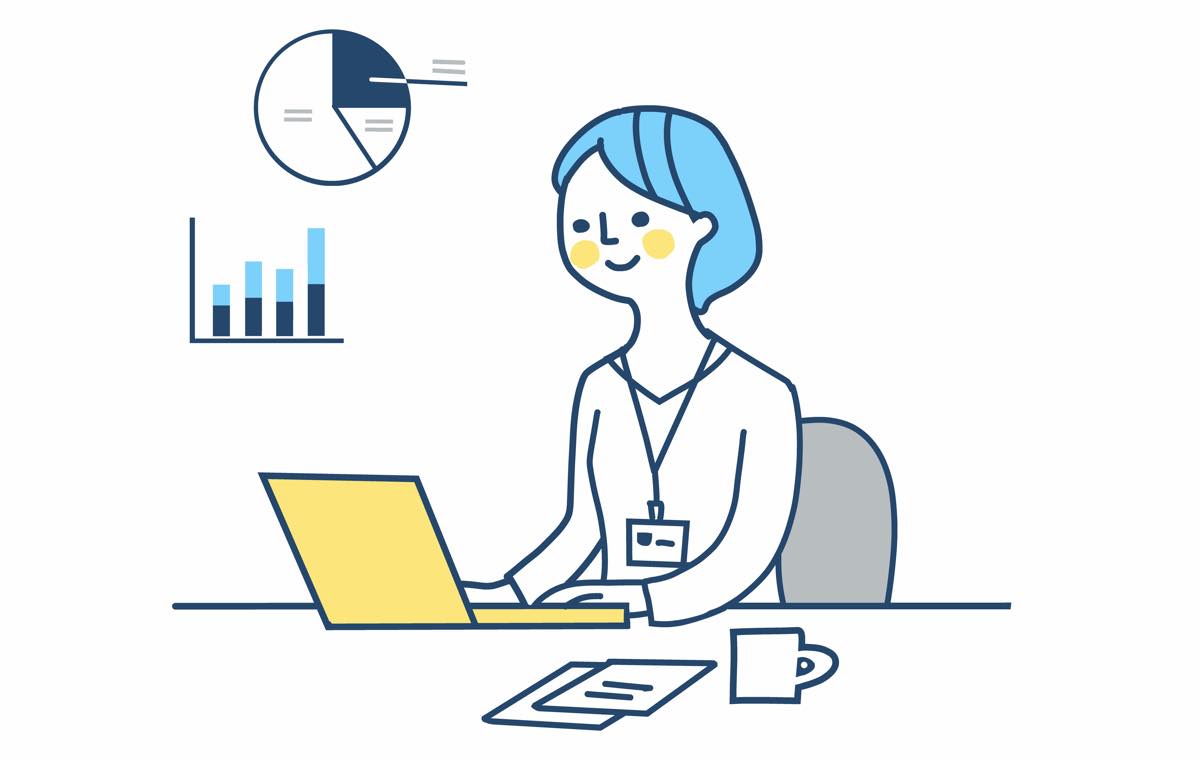
やや堅い「承りました」
「承る」は辞書で、次のような意味を持つとされています。
[動ラ五(四)]《上位者から命令などを「受け」「いただく」の意の「受け賜る」から》
(中略)
4 引き受ける意の謙譲語。謹んでお引き受けする。「御用命—・る」
出典:小学館 デジタル大辞泉
「承る」という言葉自体に、謙譲の意味合いがあるということです。電話応対やクレーム処理などで使うと、丁寧な印象を与えられるでしょう。
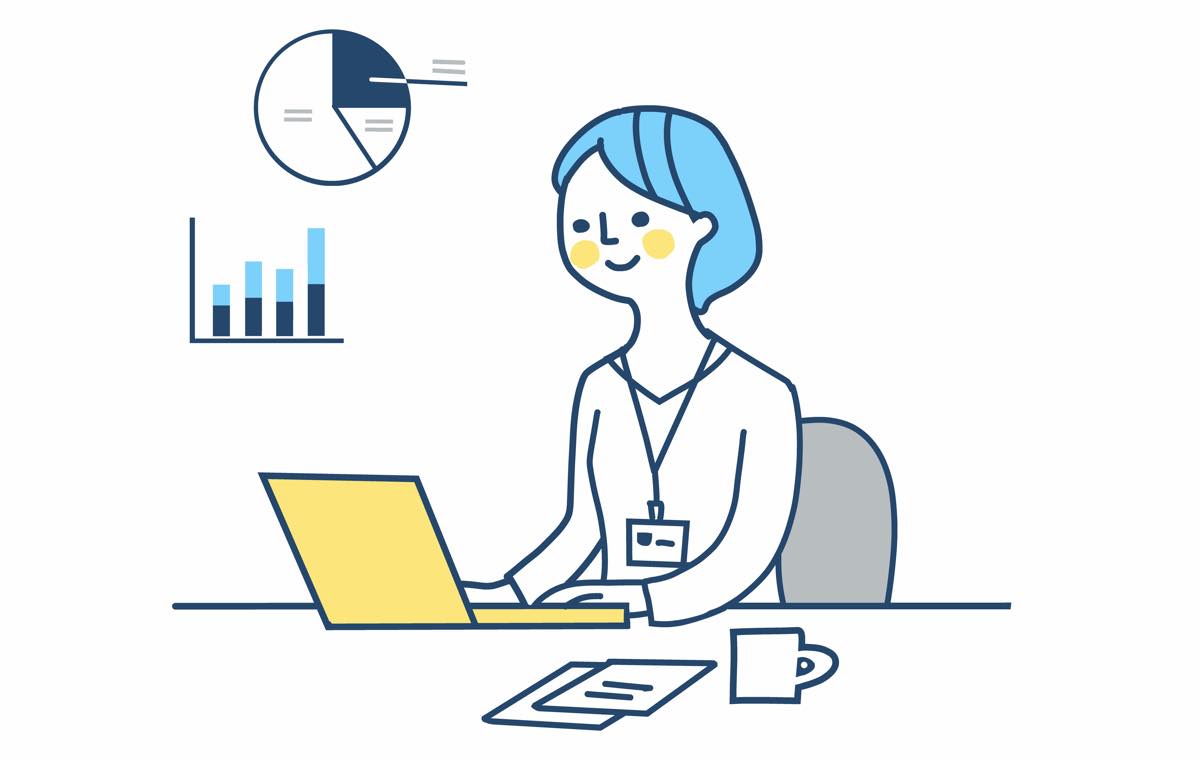
「承りました」は「承知いたしました」より丁寧で堅い敬語とされています。堅い表現なので、社内で頻繁に使うのは違和感がある場合も。
よりビジネスライクな表現「引き受けました」
「引き受けました」は文字通り、依頼を引き受ける意思を伝える丁寧語です。謙譲の意味合いはないため事務的ではあるものの、責任を持って対処する意思を表現する場面には適しています。
ただし、事務的・ビジネスライクでドライな印象を与える可能性に注意が必要です。同じ意味合いで丁寧にするなら、「お引き受けいたしました(いたします)」と謙譲表現にするとよいでしょう。
まとめ
- 「かしこまりました」は接客的・丁重な印象、「承知いたしました」はよりビジネス向き
- 相手との関係や使用シーンによって使い分けると印象がよくなる
- 類似表現の使い分けも押さえると、言葉選びに迷わない
ビジネスシーンでは、言葉遣いが印象を左右する場面が多々あります。「かしこまりました」と「承知いたしました」や類似表現の違い・使い分けを理解しておくことで、メールや会話での表現にも自然と自信が持てるようになるでしょう。
画像:(c)AdobeStock
TEXT
Domani編集部
Domaniは1997年に小学館から創刊された30代・40代キャリア女性に向けたファッション雑誌。タイトルはイタリア語で「明日」を意味し、同じくイタリア語で「今日」を表す姉妹誌『Oggi』とともに働く女性を応援するコンテンツを発信している。現在 Domaniはデジタルメディアに特化し、「働くママ」に向けた「明日」も楽しむライフスタイルをWEBサイトとSNSで展開。働く自分、家族と過ごす自分、その境目がないほどに忙しい毎日を送るワーキングマザーたちが、効率良くおしゃれも美容も仕事も楽しみ、子供との時間をハッピーに過ごすための多様な情報を、発信力のある個性豊かな人気ママモデルや読者モデル、ファッションのみならずライフスタイルやビジネス・デジタルスキルにも関心が高いエディターたちを通して発信中。
WEB Domani
あわせて読みたい